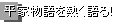
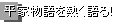
|
|
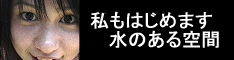 |
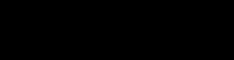 |
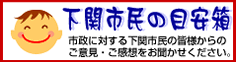 |
| [1] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月15日 12時19分50秒 ) | パスワード |
 |
「比企氏」と言えば頼朝の乳母の一族ですね。
比企朝宗は頼朝とは乳兄弟になりますね。
配流中の頼朝に物心ともに援助した一族です。
この人の娘が北条義時に嫁いで名越朝時を生んでいます。
NHK放送の「北条時宗」によると「名越氏」が本来の北条の得宗家を継ぐべき家系。
鎌倉幕府の名門中の名門であったべきですね。
| [2] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月15日 12時41分07秒 ) | パスワード |
 |
鎌倉幕府の名門中の名門である(あった)べき比企一族がどのように
隆盛を極めたのか、比企尼(ひきのあま)が歴史の中心になりますね。
比企尼:
源 頼朝の乳母の1人。
当時は乳母は1人だけではありませんから「乳母の1人」とちゃんと書いておかねば。
武蔵国比企郡を拝領。現在の埼玉県内になりますね。
甥の比企能員を猶子とし頼朝に仕えさせています。
娘河越太郎重頼の妻であったが頼朝の子供の頼家の乳母となる。
母娘2代に亘って乳母になっていますから頼朝に非常に近い存在だったこと
源家に近い家だったということが分かります。
比企尼の家には頼朝・政子はたびたび訪れているということで
関係は良かったようですね。
比企の尼の甥の能員も乳母夫として頼家に仕え、能員の娘が頼家の愛妾
(若狭局)となって頼家の外戚となったことから北条氏と対立することになりました。
建仁3(1203)年北条氏の征討を受けることになりました。
| [3] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月15日 12時59分02秒 ) | パスワード |
 |
比企能員(生年不詳~建仁3・1203年9月2日)比企能員の乱
比企尼の養子となって頼朝に早くから仕え
西海・九州への平家追討に従軍
1189年の奥州・藤原泰衡追討には北陸道大将軍となり
1190年の大河兼任の乱には東山道大将軍として出陣。
頼朝の2回の上洛の同行し
上野・信濃国守護を務め
娘の若狭局が頼家との間に一幡を生む
頼朝死後13人の合議衆に加えられ
頼家の外戚としても権勢を振るい
やがて北条氏と対立。
建仁3(1203)年8月頼家が危篤になると
時政が突然
<東国28箇国の地頭職と日本国総守護職を一幡に>
<西国38箇国の地頭職を千幡(のちの実朝)に>
譲るとした
これに憤った能員が病の回復した頼家と図って時政を討とうとしたのが政子に知れ
9月2日の仏事に事寄せて時政邸で謀殺された。
翌日迄に比企一族も滅亡した。
頼家との謀議は「吾妻鏡」に潤色の可能性がある。
| [4] |  | 源三さんからのコメント(2001年07月16日 00時24分08秒 ) | パスワード |
 |
[1]について。
明子さん今日は!名越氏の祖、名越朝時の母が比企氏の出ですか・・・。
★大友氏関係から見ますと。
1名越朝時(北条義時二男)の室(妻)は大友能直の娘(大友初代能直の娘)で
越後守光時、尾張守時章、備前守時長、左近太夫将監時兼、修理亮時幸等母。末弟の教時は違うのかな・・・。?桔梗さんも大友能直の孫なのかな?調べとこ。
2北条宗頼(北条時宗の末弟、元冦により長門国下向、長門守護。)の妻は大友三代頼泰(泰直)の娘。子の、兼時は六波羅南方、鎮西行、同じく宗方も六波羅へ。大友頼泰は同じく元冦により豊後に下向。
3北条資時(三郎、二代執権・北条義時の弟で三代執権北条時房の子で時盛の弟)妻は大友二代親秀娘。
・北条時房(和田義盛の郎で功をたて、承久の乱には兄・義時の子・泰時と共に西上、六波羅で京を治め、義時死後鎌倉に帰り幕府連署になった。丹波伊勢遠江守護)
・北条時盛(時房子、資時兄、承久の乱後、いとこ泰時の命で六波羅に赴き、京都を警護した。丹波守護)★この系統かな?以前NHKの鶴瓶と加藤茶さんが丹波を訪れる番組で、明智氏ゆかりの亀岡の大きな旧家の民家を訪れてたけど、北条さんてでてきて加藤茶さんがびっくりしていたこと思い出します、多分、丹波の北条さんだから時房、時盛の系統ではないでしょうか?他に地元の旧家で明智氏家臣の宇野家にも訪れていてその家、敷地の広さにお二人驚いていました。
★追加、三浦平氏と大友氏の関係 1
三浦(三代)義継の一人娘は波多野(大友)四郎経家妻で二人の娘は大友能直の母。
わかりにくいですね、ようするに大友(初代)能直の(母方の)祖母が三浦義継娘。
桓武天皇-高見王-高望王-良文(村岡五郎、兄に国香「平家嫡流、北条、大掾氏祖」良兼、良将「平将門父」がいる。)-忠通(村岡小五郎、弟・忠頼は千葉、秩父・畠山、土肥祖)-為通(次弟・景通は梶原・鎌倉氏祖、三弟・景村は大庭祖)-
為継-●義継(三浦)--義明-------杉本義宗(太郎)---和田義盛
| |
-岡崎義実 -三浦義澄(次郎)×--三浦義村×
|(三浦介、源頼朝の創業従う相模守護)
|
-佐原義連(十郎 七尺五寸)-盛連-
和泉紀伊守護 L家連-女(★大友頼泰母)
(紀伊守護)
----盛時(盛連子、義村・泰村親子滅亡後・三浦介)---続く。
L芦名盛宗(相模芦名住)
高望王-三浦良茂(良文弟)-良正-公義(弟・到成の孫は鎌倉氏祖、その孫・景忠は大庭祖でその弟・景長の子が梶原の祖、梶原景時、その子が梶原景季)-為継-義継-義明。(三浦氏の別系図)
2大友(三代目)頼泰の母は三浦肥前守(平)家連娘。(佐原家連娘)
(初名・泰直、鎮西「東方、一方」奉行、豊後、筑後守護、のち筑後守護は1277以降、北条宗政に。蒙古襲来鎮西下向、著名な「蒙古襲来絵詞」には大友頼泰の勇姿が描かれている。)
三浦氏と大友能直の母方祖父の波多野四郎(大友)経家の波多野家は源家累代の家人の家柄で、代々源家当主が源義家以来、波多野、三浦の当主、一族の烏帽子親になっている。(擬制的親子関係を結び将来に亘って援助していく体制を約束するもの。その証に源氏一族と共通の通字「義」を与えた。三浦氏の場合、義継、義行、義実、義澄、義連、義宗、義盛、義村の「義」を実名に用いてることからも事実だろう。波多野氏の場合、遠義、義通、義景、義常、高義、義職、義定、義泰、義典、義和、義忠の名からみてわかる。)なお波多野遠義娘の坊門姫は、源義朝二男、源朝長の生母であり、波多野四郎(大友)経家(大友能直祖父)の妹である。波多野当主は次郎義通で、弟・河村三郎秀高、坊門姫(源頼朝兄の源朝長母)、波多野五郎義景(和田合戦で失脚。長門、伊勢、甲斐波多野祖)、菖蒲七郎六郎実経、沼田七郎家通。
*余談・源範頼、義経平家追討で西国に向かう。波多野経家、実方らこれに従う。
1184年1月。
*波多野経家(大友能直祖父)鎮西から鎌倉に帰参し源頼朝に西海合戦の模様を語る。1185年4月。
あと三浦義明娘と源義朝の間に生まれたのが、悪源太・源義平です。
3大友氏と他の平氏系の関係
大友(二代)親秀の母は畠山四郎入道娘(高山四郎重範娘、重範は畠山系高山氏祖の重遠の四男、重遠の兄が河越祖・重隆、弟が江戸氏祖・重継。)
追伸、服部さん名越氏は全滅しましたね。一部の子たち除いて。
のちの豊後大友氏一族(家臣)に名越氏の名前がちょくちょくあるのはやはり縁戚の元冦で豊後に下向土着した大友氏を頼っていった一族いたのでしょうかね・・・。
それと服部さんも「苗字・名前・家紋の基礎知識」お持ちなんですね?確か渡辺三男著、新人物往来社のもの。これは詳しくて安くていいですね・・・。一様私先祖はp126の一番右下に載ってます。あとp100下から二行目の右の氏族の中にあります。
あと服部氏の記述もp165、166にありますがこれ書き込もうと思いましたが服部さんがこの本をもってらっしゃるのなら、書き込みは控えさせて頂きますがどうでしょうか・・・。?ではでは。
| [5] |  | 源三さんからのコメント(2001年07月16日 01時12分35秒 ) | パスワード |
 |
★追加、三浦平氏と大友氏の関係 1
●上記の無茶苦茶な三浦系図の訂正です。
三浦(三代)義継の一人娘は波多野(大友)四郎経家妻で二人の娘は大友能直の母。
わかりにくいですね、ようするに大友(初代)能直の(母方の)祖母が三浦義継娘。
桓武天皇-高見王-高望王-良文(村岡五郎、兄に国香「平家嫡流、北条、大掾氏祖」良兼、良将「平将門父」がいる。)-忠通(村岡小五郎、弟・忠頼は千葉、秩父・畠山、土肥祖)-為通(次弟・景通は梶原・鎌倉氏祖、三弟・景村は大庭祖)-
-為継-●三浦義継--義明---杉本太郎義宗-----和田義盛
L岡崎義実 L 三浦 義澄(次郎)×-三浦義村--泰村
| (三浦介・源頼朝創業に従う、相模守護)
L佐原義連
紀伊、和泉守護-----盛連-盛時(三浦介)
十郎、七尺五寸 L家連(紀伊守護)-女★大友頼泰母
高望王-三浦良茂(良文弟)-良正-公義(弟・到成の孫は鎌倉氏祖、その孫・景忠は大庭祖でその弟・景長の子が梶原の祖、梶原景時、その子が梶原景季)-為継-義継-義明。(三浦氏の別系図)
2大友(三代目)頼泰の母は三浦肥前守(平)家連娘。(佐原家連娘)
(初名・泰直、鎮西「東方、一方」奉行、豊後、筑後守護、のち筑後守護は1277以降、北条宗政に。蒙古襲来鎮西下向、著名な「蒙古襲来絵詞」には大友頼泰の勇姿が描かれている。)
| [6] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 01時40分04秒 ) | パスワード |
 |
源三どの:
関東は坂東8平氏の本拠地ですから
頼朝の御家人になった(大多数の藤原氏系・平氏系それから少々源氏系の内)
中心人物達は殆どが平氏系なので、
この人達が平氏内でも婚姻関係をもって親戚だからややこしいですね。
この近親?関係が頼朝の死後どこがトップになるかで争って頭1つ抜いたのが北条?
ほとんど団栗の背比べなんで反北条勢力も凄じかった?
だから北条執権政権の仕事の中身は敵対勢力の粛清に次ぐ粛清?
そこへ降って涌いたのが「蒙古襲来」事件。
これで北条は悪名を吹き飛ばして精算出来た?
源三どのの所も大友氏から起こして新しいスレッドをお立てになりませんか?
大友氏はもともとが藤原秀郷の子孫で足柄の大友にいたのが豊後守護に任じられた
初代能直以来鎮西奉行として氏泰の時に足利尊氏と父子の関係を結んで以来源氏を称し、
宗鱗の時北九州一帯を領するに至った名門。
「姓」を替えるというのは結構あるようで
エライ人のお声掛かりなら周りや一族も反対はないでしょうし
江戸時代も徳川幕府は大大名などに「松平姓」を下賜してるし。
上記の家系図を拝見してると
梶原と大庭がもとは同族だったのが
とんでもない運命をお互いに歩むことになって行くのが見えてきますね。
平家の時代、3男の家の大庭家の方が梶原家より上に立ってたから
だから
梶原景時は洞窟に隠れていた冴えない頼朝を見ぬ振りをして大庭の鼻を明かしてやっただけのことだったのではないのか?
ところが
その後頼朝は強運に恵まれて大勢力に成長してしまい
梶原の出来心が大功に繋がってしまったけど
実は元は梶原の大庭に対するほんの小さな嫉み心からだったのではないか?と
系図を見てるといろいろ思い浮かんで来ます。
こういうの考えてると実に楽しいですね。
系図から話し掛けて来る声。
こんなのキャッチ出来た時が面白いです。
| [7] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 01時50分04秒 ) | パスワード |
 |
さっき思い出しましたが
義経の正妻は河越太郎重頼の娘でしたよね。
それで義経に縁座して頼朝に謀殺されて所領は妻の物に。
なんという親戚関係でしょうね。
比企尼にとって娘の婿が河越重頼では満足出来なかったって事なんでしょうかねぇ?自分の娘より寵愛する女性が河越重頼にいたのかも知れませんね。
それであんな婿ならいない方がいいから
殺して財産を娘に?
比企尼は猛女だったのかもね?
| [8] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 01時54分49秒 ) | パスワード |
 |
女性問題の他に考えられるのは
河越重頼が義経を高く評価してたのでは?という推測。
昔は母が異なれば冷たいもんでしょうから
母の違う義経を高く評価する重頼を頼朝命の比企尼や娘には面白くなかった?
| [9] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 02時24分01秒 ) | パスワード |
 |
比企氏も藤原秀郷の子孫で能貴が祖、と書かれていました。
| [10] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月16日 21時28分06秒 ) | パスワード |
 |
折角、明子先生がこのような立派な場所を与えて下さったので、少し気恥ずかしいのですが、コメントすることに致します。少しずつ上達致しますので、お付き合いの程宜しくお願い致します。
鎌倉を騒がせた『比企』筋の女達(前編、5名)
① 比企禅尼
1159年『平治の乱』後、平清盛の継母『池禅尼』の嘆願により、伊豆の蛭ヶ小島へ流された『源頼朝』(当時13歳)の後を追って、夫『比企掃部允』と共に武蔵国比企郡(埼玉県松山市付近)に住み、その後約20年間、源氏再興まで何くれと無く、生活の資を送り続けた。
夫、掃部允が1180年早世後、『後家』となっても、陰ながら見守り続けたと、吾妻鏡に記されてある。
比企尼には3人の娘達が有り、
長女『丹後内待』は京都では『惟宗広信』との間に『島津忠久』『若狭忠季』を生んだ後、武蔵では安達藤九郎盛長(頼朝側近)の妻で、後に源範頼の妻を生んでいる。
次女は河越重頼(武蔵豪族)の妻で後に源義経の正室を生んでいる。
三女は最初、伊東祐清(伊豆豪族)に嫁ぎ、後に『平賀義信(源氏)』と再婚し、『平賀朝雅』を生んでいる。
いずれも、1182年2代将軍『源頼家』が『比企館』(鎌倉比企谷-現妙本寺)を産所にして生まれると、将軍世継の乳母として列せられた娘達である。
その時,既に『尼』は年老いていたと思われるが、鎌倉殿として押しも押されぬ貫禄を備えた育て子の「頼朝」を仰いで全盛期の状態にあったものと推察する。
その後、比企尼の娘達の悲劇が連続して始まるのであるが、「比企尼」はどうもその前段の事件は遭遇しているが、後の比企の辿る運命を知らずにこの世を去ったようである。(享年知れず)
せめてもの安らぎを覚える。
悲劇の大きなものだけを記すと
①1189年(文治5)次女の嫁ぎ先である河越重頼の娘婿『源義経』が奥州衣川 館で殺された時、4歳の娘と共に散っている。壮絶な死で あったとされている。(河越氏は滅亡も、後家に河越領が 継がれたとある。)
②1193年(建久4)長女『丹後内待』の娘婿『源範頼』が伊豆修善寺にて自刃
安達家はしばらく歴史から消える。
③1203年(建仁3)養子『比企能員』と娘『若狭局』世継『一幡』が北条時政 に殺害(自害)、いわゆる『比企の乱』
④1205年(元久2)三女の嫁ぎ先『平賀義信』の実子『平賀朝雅』が北条時政 及び「牧の方」の陰謀に組したと言う事で京都で討たれ
る。
以上が「比企尼」の言われである。主に、嫡女「丹後内待」の娘の嫁ぎ先「源範頼」の子孫とされる「吉見系図」を参考とした。
「比企尼」の姿を想像する。(小生の主観)
*人は、このような偉大な「尼」に出会うと、すぐに、西洋のマリアの様な救世主 を想像してしまう。しかし、私はそうは思わない。
*そんなに易しい人生ではなかったと思っている。人生そのものが「修行」のよう なもので、戦いの連続であったと想像する。本人は意識していないが、
*普通の常識では計れない人生であったと考える方が妥当ではないでしょうか?
*多分、武田鉄也が表現する九州のタバコ屋の女傑が正解である。
一度にあまり長く書くと疲れるので、又次回にします。次回は「丹後内待」につい て書きます。
| [11] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 22時49分50秒 ) | パスワード |
 |
他の2人の娘達の一生も苛酷だったのですねえ。
範頼や平賀の妻になってるのは知りませんでしたが
北条氏にとっては目の上のたんこぶだったのですねぇ。
ありがとうございました。
次回のお話、楽しみにしております。
| [12] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月16日 22時57分13秒 ) | パスワード |
 |
範頼や平賀氏が殺された経緯には妻の実家にも原因があったかも知れませんね。
北条氏の陰謀は麻のように絡み合ってなかなか真相に迫らせませんね。
いよいよ北条氏というのは凄い一族だったように思いますね。
藤原貴族ならいざ知らず、日本の武士でこういう家って、珍しいんじゃないでしょうかねぇ?
私には時政や政子があっかんべ~をしたような気になりましたよ。
| [13] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月17日 22時43分52秒 ) | パスワード |
 |
*丹後内待について 丹後内侍は鎌倉時代を代表する『最後の御家人…安達家』の祖とも言うべき『安達藤九郎盛長』に嫁いだことで有名である。
その前、京都時代に『惟宗広信』に一度嫁いでおり、薩摩藩の祖と言われる『島津忠久』と『若狭忠季』比企禅尼の長女 を生んでいる。 『丹後内侍』が歴史上、名前が出るのは『源範頼(頼朝の弟)』の妻に安達盛長との間の娘を嫁がせているからである。 1193年(源範頼生害の時)6歳になっていた嫡子は父と共に自害して果てたが…4歳(範円)2歳(源昭)は『比企尼』と『丹後内侍』の助命嘆願により、「武蔵国比企郡吉見庄」を範円の子『為頼』に与えられたと『吉見系図』に記されている。 同じように、滅び行く『比企家』の跡を最後までカバ-した『御家人』は『安達家』であったと考えられる。
『安達家』は『安達藤九郎盛長』の嫡子『景盛』の娘(後の松下禅尼)を3代執権北条泰時の嫡子『時氏』に嫁がせている。 『松下禅尼』は700年後の今日にあっても、『良妻賢母』の手本とされる『子育ての才女』であった。『比企尼』の長女『丹後内侍』の孫娘にあたるのは単なる偶然では無いと思われる。(比企尼の20余年の頼朝の世話に通じるものがある)
その後、『安達家』は意識的に『北条氏』との婚姻関係を深めていくことで、『三浦氏』に代わる『御家人』筆頭の位置を確保する。8代執権『北条時宗』の父はこの『松下禅尼』の次男『北条時頼』である。
『比企尼』の嫡女「丹後内侍」は実質的な『比企尼』のブレ-ンとなって京都では公家社会に深く入り込み、『尼』が武蔵国に下ると共に京を捨て「行を共にしている」、武蔵に住み着いてからの『婿』…安達藤九郎盛長は先に結婚してから、『比企尼』の命で『頼朝』に仕えさせたと言うのが実態のようである。 その意味では『丹後内侍』は『安達家の祖』的な存在の人であったと考えられる。
後の北条執権の隆盛時代(頼時…時宗)に『安達家全盛期』を迎えるのであるが、『丹後内侍』は地下で何を考えていただろう?
*丹後内待の人柄を想像する(私の主観)
時代的な背景は別にして、私は「比企尼」以上の激しさを感じる。一番不可解なのは、明子先生も前に触れられている、京都での「島津忠久」の頼朝のご落胤説や、実質的な「安達家」の滅亡の直接的原因とされる。「安達景盛」の頼朝のご落胤説などが付き纏うのは、ある種の「妖婦」的な印象が離れない。
多分、あの「嫉妬心」の深かったとされる「北条政子」の逆鱗に触れぬはずがない。 私は、この「丹後内待」こそ全ての悪夢の元であると思っている。
*若狭局について
比企筋の女性で一番高い位置にあって、一番悲しい最期を迎えたのが『若狭局』である。別名『讃岐局』と言われる。
比企尼の養子『比企能員』と渋河兼忠の娘の間に生まれた『比企家』直系の娘で祖母『比企尼』の力で頼朝の嫡子である2大将軍『源頼家』の側室となり、世継『一幡』を生んでいる。
1203年『比企の乱』で「比企能員」が北条時政に誅殺され、翌日、鎌倉比企谷の『小御所』において『一族』全てが『一幡』を道連れにして自害すると言う、痛ましい最期を遂げるのであるが、
当時(鎌倉時代)の習慣からすると、『若狭局』の考え方さえしっかりしていれば、「生き延びることは可能であった(女子には寛大)」と考えると、
何か『若狭局』の育ち(お嬢様)と人の良さのようなものが滲み出て悲しくなる。
作家平岩弓江さんが小説『かまくら三国志』のなかで『比企三郎』を中心にして、この若狭局との兄妹愛を描いているが、多分平岩さんが描いたような人であったように思えてならない。
もう一つの『ロマン』は『若狭』と言うことばである。父『比企能員』は35万石程度の領地を治ていたとあるが、『北陸大将軍』に任じられていたともある(吾妻鏡)。
上記の『丹後内侍』は京都時代に惟宗広信に嫁ぎ『島津忠久』と『若狭忠季』を生んでいる。
結果として、江戸時代『越前福井藩…比企家』が現在の「比企家」の出所となっていることが何か因縁めいた関わりのようなものを感じて、謎(不思議)と『ロマン』を秘めている。
参考までに『小御所(比企館)』で最期を遂げた『若狭局』の兄弟:姉妹達をあげると……嫡子(兄)比企余一兵衛尉、比企三郎、比企弥四郎時員(先祖)、比企五郎、河原田次郎(娘婿)等である。
他に、難を逃れた子孫は…『比企能本圓顕(鎌倉妙本寺開祖)弟…当時2歳』『竹御所(鞠子)当時2歳…実子』
*若狭局の人柄についての想像(私の主観)
作家、平岩弓枝女史が「かまくら三国志」の中にえがかれている「若狭」が見事に当たっていると思っている。比企の女性史の中で唯一、「女の子」らしい女の子はこの「若狭」だけである。たくさんの鬼が出てくる中で、ひときわ目立つ存在の「若狭」に拍手をおくりたい。
*竹御所について
源頼家の子供は正室『辻殿』の生んだ『公暁』(実朝を殺害した)の他に数名数えられるが、…
末子で『若狭局』の娘とされている。何故なら、鎌倉比企谷『妙本寺』内に『比企能員一族の墓』『若狭局:一幡の墓』藤原頼経の正室『竹御所の墓』が全て集まっている。
妙本寺縁起による比企能員の末子『比企能本』が晩年に開山したとある。
竹御所については、最近特にその存在が注目され出した人である。
『源家』最後の血筋として、3大将軍『源実朝』亡き後、京都の藤原(一條)家から4大将軍『藤原頼経』を迎えるに際して、頼経は頼朝の妹の婿『一條能保』の家系をひく九條道長の子『三寅』であるが、『血筋』として『源家』の『血』を濃くする必要があった。
特に、執権北条氏としては『御家人達』に対する手前どうしても『源氏』の血筋が問題視されたと考えるべきである。
1216年、『北条政子』の命で『竹御所(名:鞠子)』は実朝の室(坊門信清の娘…未亡人)の養女にされている。
1219年(承久1)2歳の『三寅』が鎌倉に下向した時、竹御所は既に17歳であった。23歳になった時、政子は69歳で亡くなった。翌年1226年(嘉禄2)三寅は元服し9歳で征夷大将軍になった。
1230年(寛喜2)に藤原頼経と竹御所は13歳と28歳で結ばれている。
1225年『政子』が69歳で世を去った時、竹御所が『葬家御仏事』を沙汰している。これは、鎌倉将軍家の中に於いて『実朝夫人』が既に京都にあり、『政子』が死んだことで、実質的に『嫡女』として位置付けられていることを意味する。
又、1231年頼朝の実子『貞暁』が46歳で高野山で死んでいるが、その時も『唯一人の血縁者として、喪に服している。』ことから、『竹御所』が鎌倉将軍家の『カリスマ』的な位置にいたと考えられる。(特に最近になって、鎌倉幕府の政治史上、再評価されはじめている。)
*竹御所の人柄を想像する。(私の主観)
この人は「謎々」である。最近の学者の説はこの人に集中している。次第に、北条の基礎が固まったころ、どうしても、「源氏」の血が欲しくなった。又うまく「竹御所」を掴まえておかないと「御家人」や『朝廷』に利用される可能性は極めて高かった。
そんな中で、彼女は結構うまく立ち振る舞っていたと想像される。
特に、源氏の血の最後の灯として、涙を誘う『死産』と、それに伴う『高齢出産死』が無ければ、歴史は違った展開をしていたのでは、
*姫の前について
京都守護『一條能保』の配下で後に京都守護職を勤める『比企藤内朝宗』の娘であり、『比企能員』の姪にあたると言われている。
頼朝の口添えで、1192年30歳の北条時政の嫡子北条義時に嫁いでいる。
北条義時の妻『決して離婚しません!』という祈請文を頼朝が義時から取ったという話は有名である。地味な義時の『恋物語』として語り継がれている。
『姫前』は北条義時のもとで『北条朝時(名越)』『北条重時(極楽寺)』の二人を生んでいる。
三代執権『泰時』の出目(?)に比べ『名越流』『極楽寺流』いずれも『本家直系』に位置しながら、『姫の前』のその後の消息が不明な点と、何となく、北条家の中での「遠慮がちな位置付け」が気になってならない。
特に『重時(極楽寺)』の系統は優秀である。北条一族の側役的な役割を十二分に発揮している。
又、『比企の乱』後50年の経過で『比企』に関わる人々が北条家の中にも、集まってきていたと考えられる。
北条重時の娘は北条時宗の父『時頼』に嫁ぎ、『時宗』を生んでいる。時宗の母は『姫の前』の『実孫』に位置することになる。
ここにも、『比企の娘』の血が流れている。
『比企家』の宿敵『北条一族』に対して、あの栄華を極めた両家が頼朝の仲介でもって、縁組されたのがこの『姫前』と『義時』との一組だけであったと言うのも不自然で、本来他にも「たくさん」の良縁があったと推察するが、後の世に語り継がれた話『吾妻鏡』(北条氏の歴史書)によれば、史実を消し去った部分があるのでは無かろうかと思う。
その意味で、当件(姫前)についても、又その系晋である北条:名越流、極楽寺流の両家が『弱々しく』感じられてならない。
しかし、想像ではあるが、1203年『比企の乱』により壮絶な最期を迎えた『比企一族』がその後、今日まで続いてきた血脈の裏に『竹御所(若狭局の娘)』と『姫の前(比企朝宗の娘)』と『丹後内侍(比企尼の嫡女)』の存在が見え隠れする。
*姫の前の人柄について思う(私の主観)
私はこの姫が好きである。比企の乱以降、消息を絶つのであるが、私は生きていたと思っている。これは、あくまで『小説』の世界の話であるが、あの恐ろしい『北条一族』のど真ん中にそそり立った「この姫」は、一番、正々堂々としていて、気持ちがいい。
NHKの『大河ドラマ』北条時宗のなかで、暴れまわる『桔梗』と『涼子』の無茶苦茶さが、私の心を捉えて話さない。
最後になりますが、鎌倉幕府を滅ぼす、足利尊氏の妻が、最後に残る、「北条」の中の『比企』、極楽寺流(重時)の子、赤橋流(長時)の曾孫『登子』(最後の血)であったのは、考えすぎであろうか???
少し、長くなりすぎました。歴史の時間のようで面白くありませんね!!
又、続きを書きます。予告、は『比企の乱』後100年の残党の戦い!
| [14] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月17日 23時36分25秒 ) | パスワード |
 |
頼朝ご落胤話は有名ですね。いつもウッカリ忘れていますが。でも比企一族に係わりがあったとは気がつきませんでした。伊東の娘に手を出しているのですから比企の娘に手を出していないのが不思議ですよね。それこそ比企尼は大喜びだったと思います。
安達との関係。これも驚きでした。昔は何重にも婚姻を通して繋がりがありますから安達と比企が親戚であるのは当たり前。
頭の中を整理して読み直しますね。
| [15] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月21日 00時28分51秒 ) | パスワード |
 |
ここに私が述べる『比企残党100年(1世紀)の戦い』は創作である。
『源義経』と言う人がこの世に出現し、人々に、壮大で派手な『ロマンチズムの夢』を与えた影に、又『静御前』の美しい悲話の裏に、歴史の本当の壮絶なドラマが潜んでいたと言う設定が私の創作なのです。
同じような意味で、鎌倉の歴史が『吾妻鏡の北条一族』に支配されてしまっていることに憤慨しているのは私だけではないと思います。
北条得宗時代の華々しい『建前』社会を目にしながら、その裏面史に潜む『本音』のドロドロしたものを『比企筋の女達』が、露骨にぶつけている様に思えてならない。
『比企の乱』の前触れとなった不吉な悲劇の戦い第2弾は、なんといっても、
1189年 源義経(奥州平泉…衣川)自刃、河越氏の滅亡が事の始まりであったと考える。
1184年9月武蔵河越荘の河越太郎重頼の娘が、頼朝の声掛りで義経の正室とされた。頼朝の乳母比企尼の孫である。
鎌倉幕府成立に伴い、頼朝の比企一族に対する『流人時代の恩返し』は大変なもので、比企能員の幕閣への登用、その娘『若狭局』を嫡子頼家の妻とする等々…
『義経』にとっては、比企一族の娘に繋る武蔵の豪族『河越氏』から正室を迎えたことが、頼朝の認知の証しとして考えられただろうが、
その時『歴史が動いた』と言えば少し大げさかもしれないが、比企はその時、大きな運命の分かれ目を背負わされたのであった。
史実によれば、源義経の最期に臨んで、正室『比企尼の孫娘』は坂東武者の娘らしく4歳の娘を道ずれに奥州衣川の地で壮絶な死を共にしている。
『静御前』の華々しい恋物語の影で、痛々しい『比企尼」の孫娘の死が比企の悲劇の始まりを予言していたのである。
明子先生が指摘する『河越氏』滅亡の後処理が『河越尼(比企尼の次女)』に河越荘を相続させている不自然さは残るが、歴史家は当時の土地相続の考えは女性中心であったと分析していることから考えると、そうなのかなあと思ってしまうが、
『比企尼』と『丹後内待』と『河越尼』の女性達の画策があったと想像しても、決して考え過ぎではないと思う。
比企の乱の余震は鎌倉幕府成立の翌年に、もう一人の頼朝の、『範頼』排斥として
起こっている。
1193年 源範頼(修善寺)での自刃である。 『比企尼』の嫡女『丹後内侍』が安達藤九郎盛長(頼朝近臣)の妻であり、その娘(比企尼の孫)が『範頼』の妻とされていた。
源範頼が伊豆修善寺で嫡男と共に誅殺される時。『比企尼』と『丹後内侍』の必死の助命嘆願で次男範円(4歳)と三男源昭(2歳)は命ばかりは助かったらしい。
源範頼の子孫とされる『吉見家系図』によれば、家系の祖を比企尼に置いて居る。又『安達家』の鎌倉御家人としての存在が大きなものであった事を示している。
『比企尼』の「ブレ-ン」的存在の嫡女『丹後内侍』の知的な謀は『安達家』を通じて『北条一族』に対抗した様に思えてならない。
私の想像では、この『範頼』の排斥は、『北条政子』の考え(頼朝死亡説)によるもので、何か「うさんくさい」ものを感じる。
又。この戦いが『政子』対『丹後内待』の対立軸を一番はっきりと解かるようにしている点に興味を抱かさられる。
頼朝を中心とした『政子』と『丹後内待(比企家のブレーン)』の三角関係が、恐ろしい女の嫉妬の戦いとなって繰広げられたのではと考えている。
『河越家』も『安達家』も『比企』のお陰で迷惑したのが本当のところであろう。
『安達家』も範頼事件以降しばらくは、歴史の表から姿を消すことになる。
比企本家の戦い(関が原)は、なんといっても、1203年 比企(一族)の乱での族滅である。
1203年9月『北条一族の陰謀』と言われる『名越亭の惨事(比企能員の騙し討ち)』が起こる。
翌日にかけて、鎌倉比企谷の『小御所』に立て籠もった『比企一族』がことごとく『自害』してはてる様は想像を絶する『悲惨な光景』である。
人々はその異様な様をして永く物語として語り継いできたと考えられる。
特に、その後の『比企一族の残党』達が100年に渡り、手を変え品を替えて『北条得宗家』に襲い掛かる様は『女性の企て…しつこい匂い』を感じる。
又、その後の『比企一族』は『北条一族』の内に宿り、北条の内部崩壊を誘う闘いに変質して行く。
その後の戦いは、見えない女達の戦いになっていく。次回をお楽しみに!
| [16] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月21日 00時40分14秒 ) | パスワード |
 |
>頼朝を中心とした『政子』と『丹後内待(比企家のブレーン)』の三角関係が、
>恐ろしい女の嫉妬の戦いとなって繰広げられたのではと考えている。
頼朝をめぐっての女の戦い<比企編>はあったと思いますね。
政子は比企尼が死ぬまではおとなしくしてたと思うけど比企の尼が死んだ後は
自分が頼朝の女性ナンバー1でありたいというのがあった筈ですから
1番目障りなのは比企系女性だったと思いますね。
第2弾、楽しみにしていますね~
早く読みたい!
| [17] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月21日 00時50分06秒 ) | パスワード |
 |
14歳で伊豆に来て
何もする事が無いから女性に関心は持ってたと思います。
でも初恋はやっぱり
平家の息のかかった家の娘より
自分の家または乳母の縁に繋がる家の娘と考える方が自然じゃないかな?と。
何があったかは分かりませんが
頼朝は何も持ってない人ですから
子供を持つなら有力者の娘を母とする方が得だというのがあって伊東の娘に手を出したのではないかな?と長い事、思ってます。
その次が北条の娘かな?と。
源家の娘や乳母の家の娘に手を出していないというのが不思議なんです。
政子は頼朝の女癖の悪さにずっと悩んでいたから
無かった筈は無い
なんていろいろ想像して楽しんでいます。
ふふふ
| [18] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月21日 18時41分35秒 ) | パスワード |
 |
前回の「比企の乱」余震において、『義経』排斥、『範頼』排斥、『比企能員』排斥という大きな流れを、比企の悲劇の前兆として述べた(創作ドラマ)
偶然にして、頼朝の意思で『義経の室』『範頼の室』に比企の娘が関わっていただけかもしれない。
しかし、実際はその裏面で、もっと大きな『頼朝』排斥が平行して密かに進められていたと考える。
史実として、頼朝は『落馬』事故により、最中に死亡するのであるが、
これまでの、歴史は『男世界』の論理のみで作られているきらいがある。一番大きなテーマは常に「兄弟仲の悪さ」であったり、『頼朝の変質的な性格』であったり、又時には『梶原景時の悪質な讒言』などであった。それを『北条の論理(政子)』で展開している。
私は、後に出てくる『姫前』と『北条義時(嫡子)』との頼朝の仲人(起請文)説まで含めて、頼朝自身は、何とか『源氏』の血による安定した幕府体制を念じていたと考えるのである。
比企の乱で族滅の危機にさらされた時、比企の嫡男『比企弥四郎時員』の室(妊娠中ー後の次郎員茂『比企次郎員茂』)と比企能本圓顕(妙本寺開山)当時2歳は和田家にお預けになっている。
1213年 『和田義盛の乱』で和田氏の滅亡(盟友)が『第三弾の戦い』になるのであるが、比企に関わる残党達が多数和田家の影に避難させてもらっていたと考えるのが自然である。
『比企の三郎』(比企の乱で自害)の盟友、和田家の三男『朝比奈三郎義秀』は幼友達で兄弟の様な育ち方をしたとある。
比企の本家筋である『三浦一族』からすると、本来『比企の乱』の時に『比企』『三浦』『和田』の連合軍で戦うべき所、『北条義時』の戦略的切り崩しで、見事に分断され十分なる戦いにならなっかった。
私はこの時に、『北条義時』との決別(姫前のこと~以降消息不明)があったと思っている。女社会で言えば、この時点で『時政』『政子』に対するマザコン『義時』の迎合が有り、以降『名越流朝時』一派に大きな溝を作ったと言うのが私の大胆な創作である。
その中でも、朝比奈三郎義秀の比企への思い入れは想像を絶する程のものがあり、和田義盛の乱には『比企一族の残党』が多数参加していたと想像される。
『和田の乱』は『比企の残党』にとって「鎌倉」の『最後の表の闘い』であったと考えられる。
比企残党第1戦であり、完敗するのである。
次回は、比企残党の舞台を京都に移しての戦い(第二回戦~承久の乱)を書きます。
| [19] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月21日 22時21分08秒 ) | パスワード |
 |
承久の乱ですか。
いよいよ政子大活躍の巻ですね。
これに比企氏がどう係わっていたのか
非常に関心があります。
早く読ませてください!
| [20] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月22日 00時10分50秒 ) | パスワード |
 |
江戸時代に『徳川支配』が約200年以上続くのですが、特にその前半100年は『豊臣の残党』と言う言葉が何かにつれて出てきた。
感覚的に理解するならば、ちょうど現代社会における『第二次世界大戦』後約60年弱の状態にある。(身体で理解する参考になると思います)
その意味では、次第に世代(大戦の体験者が世を去り)交代が進み、『大戦の残党狩り』も人々の頭から消え始めているのが、現代の世相であると思うと、知的には少し危なく、不安な状態を呈している時代と言える。(第二次世界大戦の犯人が分かりだす頃?)
話が少しそれたが、申し上げたいのは、比企残党の戦いも時間の経過と共に抽象化が進むと言う事を申し上げたいのです。
度重なる敗戦は、想いを観念化し、『心の奥へ~』封じ込める様になっていく。例えば、鎌倉の地に立ち込めていた『復讐』の二文字が居場所を失い。京都へ移って行ったのです。
昔から、西へ行けば『浄土』が有るといわれているのは何か関係があるのでしょうか?
1221年 『承久の乱』が、予想外に鎌倉で族滅させられた『御家人』達のエネルギーによって引き起こされた事が、クローズアップされ始めている。
1221年5月後鳥羽上皇が京都守護伊賀光季を討ち、挙兵した。
源家3大将軍源実朝が鶴岡八幡宮に於いて公暁に暗殺されたことで『源氏の血筋』が終わるとの判断で、鎌倉追討の兵を挙げようとした。
後鳥羽上皇を祭る『京都武士』の大半は鎌倉幕府の政争で敗者の系譜を引く人々『梶原一族』『比企一族』『和田一族』に『木曽義仲の残党』等が構成していた。
『糟屋久季』は「比企能員」の娘婿の実家、『惟宗孝親』は「丹後内侍」の元主人の実家である。
『鎌倉の和田の乱』で敗走した『比企の残党』が舞台を「京都」に移して最後の抵抗。
比企残党第二戦である、結果としてこの戦いが表立っての『比企』の戦いの最後になっている。
『いわゆる男の論理で言う戦争(いくさ)の事である。
明子女史のご質問の『政子』の関わりについてですが~
歴史の教科書では、『承久の乱』=『北条政子の大演説』となっていますが、実際は??
追い詰められた「犯人」に向かって『警察』が「おまえが犯人だと判っているのだ!」
「手を挙げて出て来い!!」と言う状態まで『政子』がいよいよ追い詰められた状態になったと言うのが実態であったと思います。
はじめて、『姿を現した妖怪』と言ったところです。北条政子の敗戦挨拶(遺言)です。
この1221年の『承久の乱』の4年後、妖怪『政子』は1225年に69歳で死んでいる。
1230年に『竹御所』が生前の政子の意志により4代将軍『藤原頼経』の正室となり、実質的な鎌倉幕府のカリスマ的なポジションを取った。(政子は竹御所『源氏の血』に負けた)
その時点で『比企』は一度木漏れ日の日差しを受けた状態になったが、瞬間(竹御所の死)の出来事で
終わってしまう。(竹御所の無き後、頼経へ三浦家共々もたれていく形になる!)
なぜなら、『比企員企員長(員茂の子)』が武蔵の国に領地を与えられたのもその時だし、妙本寺に比企の墓を建立しているのも、その頃である。
北条得宗(時頼)の登場が流れを変える結果になる。(得宗執権体制の強化)
1246年(寛元4年)名越光時の乱が起こっている。 名越北条の粛清が歴史解釈であるが、この戦いの意味するものはそんなに単純ではない。
『名越亭』は『北条時政の居宅』で、本来『本家筋』に位置付けられる。
又当時『比企全盛期』にあって、その一族『比企藤内朝宗の娘(姫前)』を母とする『朝時(名越)』『重時(極楽寺)』は得宗家(泰時…母不詳)に対して『一物』を持っていた。
泰時の嫡男『時氏(28歳)』その子『経時(23歳)』が早世し5代執権時頼が誕生した頃、『名越北条の嫡男…光時』は次男『時幸』と共に『我は義時が孫、時頼は義時が彦なり』と『執権職』に野心をあらわにした。
結果的に名越一族から離反者が出たため『光時』は伊豆に流罪、『時幸』は自害、前将軍『頼経』は京都へ追放で決着したが…『前将軍:藤原頼経』を巻き込んでの『北条内紛』として具現化した最初の戦いである。
私はここからの『戦い』を「裏の闘い」と名付けている。別に『女性の戦い』とも定義出来ると思う。
具体的に云うと~
① 名越流朝時~光時の中に流れる『比企藤内朝宗』の娘『姫前』の血が騒ぐ!!
② 四代将軍『藤原頼経卿』の妻『竹御所(若狭局の娘)』の「想い」が騒ぐ!!
③ 比企本家筋『三浦家』の積年の苦汁が次第に限界に近づいていた。 等々
このような、抽象化された動機には、多分女性が関与した形で動いていくものである。
今年のNHKの大河ドラマ『北条時宗』の中で、見事な『好演』をしている『原田美枝子』演じる足利泰氏の妻『桔梗』の『狂』に通じるものである。小説および脚本の世界の話であるが、私は『桔梗』の存在は何よりもドラマを引き立てている。(拍手!拍手!)
次回は『比企本家(三浦家)』の滅亡『宝治合戦』について書きます。
| [21] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月22日 00時27分38秒 ) | パスワード |
 |
ほぅ~
凄いですね。
こうして追って行くと「時頼」から始まるNHK「北条時宗」の背景が分かって来ますね。
私達は時頼がすんなり執権になったとか時宗もすんなり執権になったとか思ってしまうけど
あの大河ドラマでかなり裏が見えましたけど
そのまた裏に比企氏の存在があったのですか。
確かに名越がえばってるしNHKの解説でも実は名越が北条の本筋だと紹介してました。
次回「宝治合戦」の巻、楽しみにしています。
| [22] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月22日 13時02分26秒 ) | パスワード |
 |
名越光時の乱は、前将軍『藤原頼経』の京都への追放で決着したのであるが、四代将軍『頼経』と『竹御所』(源氏最後の血)が残した「禍根」は北条得宗家(北条時頼)の反主流軍団『三浦家』を中心とした力を形成したことである。
私は、この頃の「北条得宗家」を朝廷、公家社会に非常に似た社会としてラップして想像する。
その事が「北条得宗家」の弱体化の兆しとして証明される訳であるが、
かって、「後白河法皇」の常套手段とされた、極力自分の手を汚さずに敵対するものに、相互の潰しあいをさせ、「勝った方」につく!高度な『弱者の論理』を展開し始めている。
既に、このとき準備された次のドラマ「三浦家」対「安達家」が水面下で進んでいた。もちろん
御承知の方がいらしゃると思いますが、明らかに「名越光時の乱」に加わるはずの「三浦家」を脱落させたのは、何時もの「得宗家(時頼)」の考えによるものであった。
1247年(宝治元年) 宝治(三浦)合戦は予定された「安達景盛(高野山)」の帰還を待って、「安達家」の一存の旗揚げと言う形で幕を切って落とされた。
前四代将軍『藤原頼経』(比企筋…若狭局の娘、竹御所の主人)を支えた『御家人』…三浦一族の最後の戦いである。本来なら、前年の『名越光時の乱』に連座するはずの、『三浦泰村』が北条時頼の分断作戦にはまり、動けず結果的に1247年4月、北条時頼の命により『安達景盛』『安達義景』により『三浦一族』は討ち滅ぼされた。
この時東国の有力御家人の多くが滅亡した。『毛利季光(大江広元の子)』『宇都宮時綱』『関政泰』『千葉秀胤』『長尾景茂』等、相模、武蔵国の三浦氏残党もことごとく滅ぼされた。「比企」「和田」の本家筋で『鎌倉最大の御家人』と言われた『三浦家』は実質的にはこの時「族滅」している。
参考までに、後の『三浦氏』は庶流『佐原流三浦』で北条泰時に一度嫁いでいて、和順離婚して佐原盛連に再婚した三浦義村の娘の筋で、これも『得宗時頼』の描いた絵の臭いがする。
比企残党第4戦である。しかし、この戦いも『比企』としては既に「女性(裏)の戦い」の域に入っていたと考える。三浦家は鎌倉の外様御家人(自立心のある)の巣窟であったと考える。
そして、『安達家』が唯一の御家人(外様)として残される事になる。『安達泰盛』は『時頼』『時宗』と二代に渡り『松下禅尼』に守られながら「全盛期」を迎えるのである。
次回は、いよいよNHK大河ドラマのクライマックスに追い付き「2月(名越)騒動」になります。私の好きな「桔梗」のロマンが消える日ということです。(原田美枝子さんご苦労様!)
いや、江原真二郎の演ずる「高師直」の顔を見ていると、結びは「足利尊氏」の妻、極楽寺重時の息子で「赤橋流」を名乗った北条長時の孫「北条登子」の中に「桔梗」を狂わせた「姫前」の血が流れていたと信じたい。
| [23] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月22日 23時47分25秒 ) | パスワード |
 |
今年のNHK大河ドラマ「北条時宗」は「宝治合戦」から始まった
というわけだったのですね。
ドラマの中では極楽寺重時の養女として時頼に嫁いだ涼子は
大江広元の孫というわけですか。毛利季光の娘だそうで。母は三浦だと言ってましたよね。
これで安達が御家人筆頭の座に。
| [24] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月22日 23時59分58秒 ) | パスワード |
 |
いよいよ2月騒動!
蒙古来襲を前に北条一門が骨肉の争いへ!
この2月騒動というのもよく分からない内輪の争いですね。
時宗の意向で時輔や名越を粛清に行った
大蔵頼季が後には粛清されるのですから。←んな、馬鹿な!ですよね。
そして名越の時章の息子の公時には所領が安堵された。
後でどんな美しい言葉で慰められても所領を安堵されても邪魔者は抹殺された。
北条のお家芸であることにはかわりがない。
北条はすっごい一族です。
| [25] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月23日 00時11分39秒 ) | パスワード |
 |
ここから少し飛んで時宗の死後問題になるのが「霜月騒動」ですね。
時宗の息子の貞時の乳母の夫が平 頼綱で
頼綱と安達が対立。
**<13>の 『丹後内侍』が歴史上、名前が出るのは
**『源範頼(頼朝の弟)』の妻に安達盛長との間の娘を嫁がせているからである。
まだまだ比企一族の血は続いていますね。
| [26] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月23日 00時23分28秒 ) | パスワード |
 |
そうそう、「霜月騒動」のもとになったのが
頼綱が貞時に安達宗景を(あいつは源家の将軍の座を狙っている)とザンソした事でしたね。
安達泰盛の子宗景は曾祖父・安達景盛が実は源 頼朝のご落胤だから
源姓を名乗ったこと。
またまた御落胤説を出して来てしまいました。
| [27] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月28日 00時37分40秒 ) | パスワード |
 |
1272年(文永9年)2月、26年前(1246年)『名越光時』の乱の時離反して、敗戦の憂き目を味わった『時章』『教時』が再び謀反を起こしたとされる。
一説に、『五代執権時頼』が死に臨んで『八代執権時宗』に、名越時章、名越教時、北条時輔を殺す様遺言したとあるが、定かではない。
1272年2月11日のことである。ついで4日後2月15日、京都で時宗の異母兄『北条時輔』が討たれた。このことを「2月騒動」と言う。
北条一門の名門「名越(なごえ)流祖朝時」が族滅することになる。常に北条本家(得宗)に反目し続けた「比企藤内朝宗の娘(姫前)」の血筋は、弟「北条重時」の「極楽寺流」だけとなった。
北条一族にあって、名越本家説を唱え、最も過激に名門「比企の流れ」に拘り続けた『名越流北条』であった。
比企の乱(1203年)から、約70年の歳月が経過している。既に、人々の頭から悲惨な記憶も消え去り、関与した人々の大半がこの世を去った頃のことである。
京都においても、四代将軍「藤原頼経」(竹御所)以来、引きずってきた鎌倉幕府に対する反目が一掃されることになる。
私は、この「二月騒動」が「北条壊滅1333年」の「狂い」の始まりであると考えている。『蒙古襲来(1274年文永11年)』の二年前の出来事である。
もうひとつの「不吉な兆し」はこの頃から北条一族の人々の『幼名』に「○寿丸」と言う名前が目立ち、「若死」が増え始めている。
小生なりの想像であるが、かっての「外様御家人」血筋との交わりを恐れ、次第に「内」への閉鎖的な交わり(血族結婚)が増えて云ったのではないかと考える。
疑心暗鬼が疑心暗鬼を生み! 病的な「青白い」人々の集まりを感じる。
夏休みの盛りであるが、小学生がペットショップで「カブト虫」を買ってきて、同じ入れ物の中で、3年も飼い続けると、「カブト虫」の体が次第に小さくなってついには育たなくなる。
私は、後年(この頃から)の北条一族に養殖「カブト虫」を想像してしまう。
次回は1285年(弘安8年)、安達泰盛(執権外祖父)が平頼綱(執権乳父)によって滅ぼされる「霜月騒動」を描きます。
比企の乱が北条時政(将軍外祖父)によって、比企能員(将軍乳父)が滅ぼされた、全く「反対の事件」として、同じような方法で殺戮されている。のが面白い。
| [28] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月28日 01時07分46秒 ) | パスワード |
 |
「霜月騒動」
この平 頼綱という人物の残虐性は「北条時宗」の中で結構うまく書かれていますね。
得体の知れない「八郎」という人間が時宗のお声掛かりで養子になって
出世していく。
時宗もこの八郎の人間性には一抹の不安を持ちながらも信頼していく。
これが北条一族の首を締めることになる。
では楽しみにお待ちしています。
| [29] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年07月28日 21時03分12秒 ) | パスワード |
 |
今日は土曜日、近くの書店に散歩に行きました。(奈良県香芝市の話)
そこで、ふと目に付いた「本」がありまして、
学習研究社から、2,001年8月5日第一刷発行の『歴史群像シリーズ:島津戦記』と言う発行10日前の書籍を見つけました。なんとなしに買って帰って暑いからクーラーかけて、寝ころがって読みました。
その中に、「松尾千歳(ちとし)さん」が書かれている「島津氏」の『名族の起源』という1節がありました。
明子先生と小生の合言葉(またまたご落胤説!)が載っていましたので、そのまま引用して、ご紹介します。
頼朝落胤説:
文治元年(1185)、源頼朝は惟宗忠久を南九州に広がる日本最大の荘園島津荘の下司職に任じた。さらに翌文治二年には同地頭職に、建久八年(1197)には薩摩、大隈国守護職に任じ、やがて日向国の守護職も兼任させた。この忠久が島津氏の祖である。
さて、江戸時代に作成された『島津氏正統系図』には、忠久の父は『頼朝』とあり、その誕生に関し次のような説話が記されている。
『伝え称す、初め比企判官能員の妹丹後局、頼朝卿に幸せられて身はらむことあり。
頼朝妻北条政子は嫉妬して、これを遂う。丹後局は害されることをおそれて、関東を出、上方に赴き、摂津住吉に至る。夜旅宿を里人に求むも、里人これを許さず。時に大雨はなはだしく、たちまち産気あり、よって社(住吉社)辺のまがきのかたわらの石上にうずくまる。時に狐火の闇を照らすに会って遂に忠久を生む』
このような説話は、かなり昔から伝えられていたらしく、室町時代の半ばに記された『山田聖栄日記』の中にも見ることができる。
この説にもとづいて、島津家では稲荷神を信仰し雨を吉祥として「島津雨」と称した。又、忠久が惟宗姓を称したのは、後に丹後局が惟宗広言に嫁したからであると説明している。(中略)
建仁三年(1203)に比企氏が北条氏によって滅ぼされた際(比企の乱)、忠久も縁座
してすべての所領を失っており、忠久が比企の縁者であったことは間違いない。
比企氏は、頼朝が伊豆に流されていた時に親身になって世話をした比企尼に連なる一族で、この比企尼の長女に丹後内侍という女性がいる。
『吾妻鏡』から彼女が安達盛長の妻で、頼朝と非常に親しかったことが確認でき、頼朝の弟範頼の子孫吉見氏に伝わった『吉見系図』には、丹後内侍は盛長嫁す前に惟宗広言との間に忠久をもうけていたと記されている。
この丹後内侍と『丹後局』は同一人物とみなしてよいであろう。(後略)
ここまでが、『松尾千歳』さんの説である。
同じ文脈の中で、島津忠久の兄、若狭忠季(若狭国守護職)が丹後内侍の同腹の兄弟であり、その意味で島津氏の祖『島津忠久』は越前国の守護職として出所があきらかにされている。
北陸、信州地方は比企氏が勢力基盤としていたところでもある。
後に『名越流北条氏』が管轄した地方でもあり、『比企筋』の関わりの深い地域である。
『比企氏』で最も高い地位に上り詰め、悲しい末路を辿った、二代将軍『頼家』の妻であった、比企能員の娘は、なぜか『若狭局』といわれている。
私は、この本を読んでいて、少し因縁めいたものを感じさせられたのは、その後、明治の初期、越前福井藩の『比企家』から別家した『比企福造』の嫡男「比企雅」が『神戸御影比企家』として、住み着いた場所が「住吉神社(御影)」のすぐ脇であったのは、妙な偶然である。 (丹後内侍が島津忠久を産み落とした岩の近くである)
又、江戸末期から明治維新にかけて、「六代比企榮庸の娘、ジュン」が、薩摩藩の西郷隆盛の盟友であった「橋本左内」(安政の大獄で29歳で打ち首)の師匠(松平藩家老、鈴木主税重榮)に嫁いでいる。 (いずれも、敗戦で命を落としている)
別家「比企福造」は39歳の若さで早世しているが、西南の役に参戦して、西郷軍を壊滅させた功で「高位の叙勲」を受け、福井清源寺(比企菩提寺)で末代までの「院殿号」を取り付けている。なぜ、ここまで「薩摩藩」と関わるのであろうか?
越前福井藩と薩摩島津藩と鎌倉幕府と攝津住吉(御影)がどうしてつながるのか解からない。明子先生が言う8代も立てば、皆、お友達(親戚)なのか、それとも、どこかで、糸を引く何かの力がはたらいてのことなのか、「じっと、耳を澄ますと何か聞えて来そうな気がしてならない。
夏(お盆)の夜に、少し涼しい話も良いものです。
今日はちょっと「脱線」話にしました。
| [30] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年07月28日 23時13分41秒 ) | パスワード |
 |
島津のご落胤説、かなり詳しいですね。
頼朝が伊東の娘や北条の娘に手を出す前に比企尼方の娘に手を出していない筈が無いです。
それにワタクシがこのあたりの事を知りたいと言ってて
林原さまに霊感が働いて?
この本が目に入った!というのも実に奇遇ですね。
こういう力って実に不思議です。
でも当然と言えば当然。
比企の女性の血の流れのパワーが今でも働いているのかも?!
| [31] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年08月07日 20時43分36秒 ) | パスワード |
 |
永らく、連載して参りました「比企残党100年の敗戦」も、いよいよ佳境を迎えました。今日は完結編をお送りします。
1285年(弘安8年)に起った霜月(安達)騒動は、『北条貞時』の命で、内管領平頼綱(乳父)により安達泰盛(外祖父)を急襲して滅ぼした。一連の事件の事を言う。
1284年4月4日執権『北条時宗』が死去した。享年34歳であった。
時宗の跡を弱冠14歳の『北条貞時』が継ぐことになる。貞時の乳父であった『内管領…平頼綱』と御家人『安達泰盛』の対立が深まっていった。
それは、80年前の2代将軍『源頼家』の時代に起った『北条時政(将軍外祖父)』と『比企能員(将軍乳父)』の対立に余りにも酷似した光景であった。
ことの発端は、得宗家(北条貞時)の内管領平頼綱が『貞時』に…
『「安達泰盛」の嫡男宗景が、曽祖父『安達景盛』は征夷大将軍「源頼朝」の血を享けた子であるから、源氏を名乗ってもさしつかえないとして、源姓に改めた』と言うのである。
安達景盛が果して頼朝の子であったかどうか、それを証するものは無いが、子孫の宗景が源姓を名乗ろうとしたからには何か信ずべきものか、あるいは安達家にそうした伝承があったかどうか?(一般には、平頼綱のでっち上げと言われている)
余談になるが、『推測』論として、『比企尼』の嫡女「丹後内侍」のことが浮かんでくる。
史実によれば、「安達景盛』の父『安達盛長』の妻は『丹後内侍』である。『丹後内侍』はとかく噂の人(頼朝の妾)であり、先夫『惟宗広信』との間に生まれた『島津忠久(薩摩藩の祖)』も『頼朝の御落胤』説があるくらいで、安達盛長の妻とあるが、実際に頼朝との関係は続いていたことは十分考えられる。
併せて、『北条政子(正室)』の強い嫉妬心は有名な話で、その点からも、有りそうな話である。
とにかく、80年前の『比企の乱』の再現のような事件が、『北条貞時(執権)』の『乳父』(平頼綱)と『外祖父』(安達泰盛)との間に展開されることになる。
比企の乱では、『比企能員(将軍乳父)』が『北条時政(将軍外祖父)』に誅殺されるのであるが、霜月騒動では、逆に外祖父(安達泰盛)が乳父(平頼綱)に敗れるのである。
共通しているのは、『丹後内侍(比企筋)』が関与する『安達家』が北条得宗家(貞時)の関与する『平頼綱』に破れたということは、80年前と同じことである。
『比企』は又々、『北条』に「煮え湯」を飲まされたということである。
最後の鎌倉後家人『安達家』の族滅は、もう『北条家』が戦う相手を失ったと言うことでいよいよ、『北条内部』の抗争が始まるのである。
その8年後、1293年(正応6年)に平頼綱は北条貞時の手で滅ぼされるのであるが、そのことは、ここでは省くこととする。(息子、「平宗綱」に反逆されたとある)
『比企の残党100年の敗戦』の最後を締めくくる『戦(いくさ)』を私は、1296年に起ったとされる『吉見孫太郎義世の乱』にしたい。
この乱は『マイナ-』で余り知られていない。
霜月(安達)騒動から10年間経過して、比企郡吉見荘で『吉見孫太郎義世』と言う『源頼朝』の弟で『源義経』の兄にあたる『源範頼』の末裔が源氏の血筋は『吉見』のみである…として謀反を企てたと言うのである。
『北条九代記』にかなり詳細に事の次第が記されてある。決行直前に与党の一人に「裏切り密告」が出て『吉見義世』が捕まり、白状しないまま殺されたと言う。真相は不明であるが… (吉見系図が残っている)
『吉見氏(源範頼末裔)』の庇護者の存在であった『安達氏』が安達藤九郎盛長の曾孫安達泰盛の代で北条貞時に滅ぼされたのである。
もしかしたら、吉見義世の乱は北条の安達残党狩りの最後であったのかもしれない。
最後の最後に再び『比企尼』と嫡女『丹後内侍』そして『安達家』が出てくるのが、私の『鎌倉ロマン』である。
1305年(比企の乱100年後)の嘉元の乱での北条同志討ち、『貞時』の失敗は『1333年の末路』へ転落が開始されるのである。
1333年(元弘3年)新田義貞の鎌倉攻めが実質上の『北条氏滅亡』とされるが、その戦いのなかで、山之内方面(洲崎口)に散った『北条盛時(先赤橋相模守)』の妹は、北条家、最後の『比企筋』比企藤内朝宗の娘『姫前』(北条義時の妻)の生んだ、『北条重時』(極楽時流)の子孫『北条登子』である。
『登子』は室町幕府の初代将軍『足利尊氏』の正室であり、二代将軍『足利義詮』の母である。『尊氏』の祖先とされる『足利泰氏の妻』が私の好きなNHK『桔梗』である。
『登子』を含めて、『比企筋』の女達に彩りを飾っている。
人々は『北条家』の滅亡をもって、鎌倉(北条)から室町(足利)へ、『男の血筋』の移りを説明しているが、
『北条登子(極楽寺流赤橋)』の中に流れる『比企筋(女の血)』の血筋は『足利家』の中に毅然として生き続けるのである。
『比企尼』『丹後内侍』『姫の前』『若狭局』『竹御所』等は草葉の陰で何を考えていただろうか???
しかし、史実では『この女の血筋』はマイナーな話であり、いわゆる『系図』上の話ではない。『比企家』に伝わる『比企一族』系図は『比企能員(比企の乱)』を『祖』として、展開されている。
又の機会に書きたいと考えますが… ここで、ひとまづ『おしまい』にします。
永らくのご愛読を感謝いたします。
特に、服部明子先生にはお忙しい中、お相手を努めていただき感謝感激です。
ありがとうございました。 以上
| [32] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年08月07日 23時09分12秒 ) | パスワード |
 |
素晴らしい研究発表ありがとうございました。
>『比企の残党100年の敗戦』の最後を締めくくる『戦(いくさ)』を
>私は、1296年に起ったとされる『吉見孫太郎義世の乱』にしたい。
吉見姓はもともと三河発祥ですから
なるほど範頼が関係するんですね。
どこかのHPのBBSで範頼の子孫の書き込みを見たとこがありましたが
吉見義世の乱のことは知りませんでした。
比企尼の血が足利幕府に脈々と流れる経緯に
『比企尼』『丹後内侍』『姫の前』『若狭局』『竹御所』等はやっと報われたことになりますね。
頼朝が乳母の方の女性に手を出さなかった筈が無いと思ってた私は納得出来ます。
歴史の秘密。
女性は表舞台に出られないけど血に残すことが出来るという1つの好例となりますね。
女の戦いの最強の武器は子孫を残すこと。
そして今も名字を変えて脈々と比企尼の血は続いているということですね。
林原さま、大変な作業、お疲れさまでございました。
ありがとうございました。
| [33] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年08月18日 10時58分12秒 ) | パスワード |
 |
原田美枝子さんの演じる『桔梗』が頭から離れません、フアンレターを書こうと思っていた矢先に夢を見ました。
異説「名越流北条朝時」、頼朝ご落胤説(官女:姫の前)
夢の中身は『名越流北条朝時』の夢です。
前から気になっていたのですが、『姫の前』が『北条義時』と『結ばれる』逸話の中で、『頼朝』が『義時』から「決して、離別しません!」と言う『祈請文』を取ったという話です。
一般に歴史家は、この話を『義時』の「生真面目さ」を表現するための『話』として、又、あの神経質『義時』が熱烈な恋愛、それもタブー『官女との恋』をした。など
義時の意外な一面を表す『逸話』として今日まで、語り伝えてきたのである。
私は、永く『北条義時』を「徳川綱吉」に仕えた『柳沢吉保』とダブらせている。
確か、綱吉が「お手つき中巃」を柳沢吉保に下げ渡した話は有名である。
「姫の前」は北条義時に嫁いだ時点で、既に「源頼朝」の子を宿していたのではないか?
と言う大胆な仮説を立ててみたのです。
この仮説がなぜこれまで「登場」しなかったかともうしますと、「男の歴史論理」が先行して、時(歴史上の事実)の帝王となった3代執権「北条泰時」がどうしても中心に置かれてしまい、その事実から、逆に論理を展開する癖があります。
「泰時」の母は、「阿波局」と言い、官女であったとされていますが、「不明」と書かれるか「阿波局と言われているが、定かでない」と表現されている。
その事が逆に「出生のロマン」を生み「頼朝のご落胤」説にまで広がったと考えられないでしょうか。
時の中心人物(北条泰時)、鎌倉幕府と北条一族(吾妻鏡)などが先行してしまい、最近の流行語「逆説の日本史」風に言いますと、「北条朝時(名越)」が主人公である歴史が背面で用意されていたのではないでしょうか。
私の大胆な「推論」によりますと、「姫の前(比企藤内朝宗の娘)」が北条義時に嫁がされた時は、お腹の中に頼朝の子「北条朝時」が居たという想定です。
源頼朝の心境と「北条義時」への約束
<政子嫉妬狂説>
① 北条政子の強度の嫉妬心が怖い、過去に何度(子供を殺す)も見せられてきた。
② 歳を取ってからの「子」はことさら「情」がかかる。
③ 「政子」から「子供の身(朝時)」を守れるのは、鎌倉で「義時」の所だけである。
<北条家安泰説>
④ 「時政」の亡き後、鎌倉の外様御家人に列して「北条家(政子の郷)」の安泰を図るには、『印籠(源)』が要る。
⑤ 「北条義時」は知略に優れ、功名心も強い(柳沢吉保風)、よって、かみ分けて話せば.理解、承諾すると「頼朝」は読んだ。
⑥ あくまで、当初の「義時」の心境は「姫の前(北条朝時)」を頂いて、北条一族にハクを付けて、「鎌倉幕府」の中で不動の基盤を確立する助けにしようと言う魂胆であったと思う。
<北条本家(名越)相続説>
⑦ 「頼朝」の条件として、「名越流」北条家(北条本家)を「朝時」に継がせること。
⑧ 「姫の前」をどんな事があっても「離別」しない事。例え「政子」が難題を持ち込んでも、「別れない」と約束する事。(本当の祈請文)
⑨ 「姫の前(官女)」は胸を張って「北条家」に乗り込んだと想像する。(ヒモ付き)
<朝時が官女恋文騒動を起こす:その時>
⑩ 北条義時が「朝時」19歳のころ、北条政子付きの女官(佐渡守親康の娘)に恋文を出し、夜這いをするなど執心する事があったときに示した「義絶」と言う厳しい態度は、何か不自然で陰湿的なものを感じる。
⑪ 一般には「義時」の教育熱心な生真面目さの話として述べられているが、自分がかってした事を子供にするな!と言うのは不自然で、「義絶」は執拗すぎる。自分がそんなことはしていないと身体で言っているようだ。
⑫ 頼朝が義時に弾圧的に自分の女をあてがった事への反感的な態度に見える。
<北条光時(名越)の言葉>
⑬ 北条朝時は「泰時」の前に出ないように謙虚で地味で、遠慮がちな一生を送り、泰時死去後も出家して、喪に服したとあるが、
⑭ 長男「光時」が1246年に名越光時の乱を起こした時に、
「我は義時の孫、時頼は義時が彦なり」と言って執権職に執着したとあるが、
そのまま、義時を頼朝と置き換えると、意味が明確になる!
「我は頼朝の孫、時頼は頼朝の彦(現:配下)なり」と、
なぜ、名越『朝時』は北条本家(得宗)を継げなかったか?
① 基本的な理由は「頼朝」の「七光り」が消えたことである。
② 「義時」は死ぬ前から、鎌倉幕府を北条家のものにする考えで固まっていた。
③ 「北条政子」は絶対に「頼朝」と別の女の血を受け入れる考えはなかった。
④ 最終的に「朝時」を除外したのは、「比企の乱」である。「比企藤内朝宗の娘(姫の前)」の血筋が北条家から疎んじられた。
⑤ 義時は1224年62歳で死去するのであるが、1203年(比企の乱)頃から「姫の前」の消息がプッツリと消えている。
⑥ 朝時も1206年に13歳で元服して、1212年に19歳で官女恋文事件で義絶、翌年、和田合戦に戻されるが、それ以降『遠慮がち』な立場を取っている。
北条朝時(名越)に比較して、同じ『比企藤内朝宗の娘;姫の前』の子供(義時の子)である北条重時(極楽寺)は得宗家の参謀的な位置に置かれていたのは、余りにもコントラストがはっきりしてて、『朝時』の悲運を浮き彫りにしている。
北条(名越)朝時は源頼朝が官女『姫の前』に、婚前に腹ませて、北条義時に下げ渡した後、北条義時の次男(義時と姫の前)として育てられた。(頼朝のご落胤説)
としたら、朝時の実娘で足利泰氏の妻であった『桔梗』さんの、『狂い』が如何ばかりか?、想像されるのである。
これで、私の大好きな『桔梗』さんの極楽浄土への『送り』がやっと完了するのである。
2001年8月15日(お盆)に1272年(2月騒動の無念)から730年間の霊の弔いをして、心が洗われた気持ちです。
『竹御所』も供養してあげなければならないと、何時も思っていますが、又夢に出てくるでしょう!!
| [34] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年08月18日 22時55分04秒 ) | パスワード |
 |
「桔梗」さんの怨み、やっと晴れましたね。
林原さまの書き込みがございませんでしたら
<北条時宗>に出て来る「桔梗」の存在が今1つ分かりませんでした。
名門「名越氏」の正当性を彼女が頑張って主張した。
本当は我が家こそ「頼朝公の鎌倉幕府」を継ぐ家である。
悔しかったでしょうね。
「竹の御所」にも是非名誉回復を!
| [35] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年09月04日 20時52分26秒 ) | パスワード |
 |
竹御所への熱い想い
1274年(文永11年)、二月騒動(北条名越流の滅亡…1272年)から二年後の年に鎌倉:妙本寺が開創されている。(日蓮宗長興山妙本寺の寺伝より)
その寺名の由来は『日蓮』が開基『比企能本』の父『能員』に長興、母(能員の妻)に妙本の戒名を授けた為、それを山号、寺号としたとある。
比企能本の経歴を、
『能員の末子、能員うたれける時僅かに弐歳にて…房州に流され、長なりて伯父阿闍梨の弟子として京に住し、後に清家の門生となり世の有様を見居たりたるに、…………
将軍頼経郷の御台所(竹御所のこと)は能本の姉讃岐局の子にして、能本の外姪にあたる、その此御縁により…鎌倉に下り、父の遺跡を安堵せしなり』と紹介している。
そして、『新編相模国風土記稿』には妙本寺の建立開創の理由は『竹御所の為』と記されてある。明らかに、時の『北条氏』への遠慮が感じられるが、……
『比企系図』によれば、
『比企圓顕(能員末子)』は父『能員』伏誅之時、円顕二歳母共に安房国に配流される。七歳之時に房州に従い、後鎌倉に帰って出家、号を『圓顕』と改め後に京の師采寺(真言宗)に学び鎌倉に下こう居住した。………………とある。
『比企次郎員茂』は比企圓顕の子に位置付けられてあるが、
実は、時員の男也、比企四郎時員(能員の嫡子)が父能員と同日自害の時、時員の室が胎内に子を宿しており、鎌倉を逃れ武州比企郡で『員茂』を産んだ。後、比企郡岩殿観音堂別当に育てられ、建保6年16歳で上洛、圓顕の助成もあって『順徳院』の北面武士として仕え、承久3年7月順徳院が『佐渡』へ遷幸の時、御跡を奉慕し越後国『称名寺』に住み着いた。
『比企小太郎員長』は越州産、員茂の嫡子である。
その頃、鎌倉将軍頼経郷の御台所は頼朝郷の嫡孫で頼家郷の息女『竹御所』であった。母儀『若狭局』は比企判官能員の娘也。その由を以て、比企吉見二郡、竹御所の領地を比企員長にくだされた、よって密かに越後国より比企郡に帰りて居住することとなった。
『員長』は弘長元年2月2日に武州比企郡で卒去している。
その子『比企左馬允満長』以降、武州中山村に永く住むことになるのであるが、そのことはここでは本題ではないので、別の機会にして………
1203年『比企の乱』で族滅の危機にさらされた『比企一族』に唯一の『光』として存在した『竹御所』(比企能員の孫娘)について論を進めたいと思う。
私が『竹御所』に興味をもったのは、野口実先生の『武家の棟梁源氏はなぜ滅んだのか』に出会ってからである。
その御本の結びに位置する巻末に…
『在京の武士ことごとく以て馳せ下りおわんぬ』
関東の貴女(竹御所と号す)、去月27日夭亡す。難産によってなり。在京の武士ことごとく以て馳せ下りおわんぬ。 (『百錬抄』文暦元年8月2日条)
竹御所小論…鎌倉幕府政治史上における再評価…を読んだ、その時からである。
先生は学者さんで大変な勉強をされており、事実に則した形でしか述べられていないが、小生はもっと『品位』の落した想像を交えた考えで自由に述べてみたいと思います。
折角の先生のご高説を傷つけないようにしたいと考えますが、お許し頂きたい。
では次回をお楽しみに、………
| [36] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年09月04日 22時02分39秒 ) | パスワード |
 |
この<35>のお話を分かり易くまとめてみました。
竹御所:建仁3~文暦1年7月27日( 1203 ~ 1234.8.23)
名を<女+美>子ともいう。
鎌倉2代目将軍頼家の娘。
母は比企能員の娘。
承久元年(1219)鎌倉将軍実朝が暗殺されたのち
源頼朝の血を引く最後の人物として鎌倉で尊ばれた。
寛喜2年(1230)に十数歳年下の将軍藤原頼経に嫁ぐ。
女子を死産。
難産の為自らも死去。
その死を伝え聞いた藤原定家は日記「名月記」で
「関東の貴人」の死を悼み
頼朝の子孫断絶を平家一門を根絶やしにした報いと批評した。
鎌倉比企谷の妙本寺に竹御所の墓と伝える墓所がある。
この竹御所の謎
どのように林原さまはお解きになるのかしら?
楽しみにお待ちしております!
| [37] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年09月07日 20時18分37秒 ) | パスワード |
 |
鞠子(まりこ)の????
明子先生の言われる『女+美』子(びし)と言う名前ともう一つの名前は『鞠子』と言われていたそうです。
二代将軍『頼家』が大変な『蹴毬』好きであったことから『鞠子』と名付けられたのであろうか?、定かではない。(とにかく、女+美はワ-プロに無いので鞠子の方を選びます。)
頼家の子供たち(一幡:公暁:栄実:禅暁:鞠子)5名の内で、女性で名の出てくる唯一の孫娘(政子の)が『鞠子(竹御所)』である。
1203年の比企ケ谷の小御所炎上(比企の乱)の時、何故『竹御所』が危難に遭遇しなかったか?今になっては想像に頼る以外解らないのですが、
多分、『北条政子』の館に居て助かったと考えられている。
『政子』が危難の起る事を知った上で、助けたのか、それとも偶然そうなったのかは知る由も無いが、後の歴史の展開を視界に入れて、逆に考えると、意識的に『政子』が『孫娘』を助けたと考えた方が妥当である。
その後も、『政子』は周到に、この『鞠子(切り札)』を温存して、成長を楽しみに待った節が感じられる。(勿論、『実朝』が「公暁」の手に掛かるまでは考えていなかったかもしれないが?、その後は「鞠子」への執着が際だった形を呈してくる。)
1216年、北条政子の意思で3代将軍源実朝の正室であった坊門信清の娘(本覚尼)、の猶子(養女)として、『鞠子』の籍をいれている。
1219年、『実朝』亡き後、未亡人(坊門信清の娘)が実権を握るべきところ、代わりに『北条政子』が実質的な中心にあった。その『後継者』として『鞠子(竹御所)』を位置付けていった。
人間社会にはよくある話であるが、特に見聞する話として『女帝』がしでかす『後継者』選びのパタ-ンは大半が『実孫』、特に『孫娘』が選ばれるケ-スが多い。
何故か解らないが『血縁(血の繋がり)』を重んじる考えが『外子息』より、娘婿よりも『実孫』を選ぶとされている。
私は『政子』の『竹御所』選びは必死の真剣な選定であったと考えている。
1219年以降の『北条政子』は『孫娘』である『竹御所』に総てを託した動きになっているように思えてならない。
あれだけ、『主人:頼朝』の妾たち、ことさら『比企筋の女達』への嫉妬に狂い、『比企』憎しで凝り固まってきた『北条政子』である。
一言で言えば、鎌倉の歴史は即その、総ての『比企筋』に関わった人々、一族を葬ってきた『政子の歴史』であると言っても過言では無い。
『政子』にとって、自らの『血』の繋がる人々(わが子を含む)までをも殺戮してきたのが現実である。
勿論、自分から直接手を下すことはしなかったかもしれないが、結果的には、身内を全て葬っている。
そして、最後の独りが『鞠子(竹御所)』であった訳です。その人が残念(政子にとって)なことに、皮肉にも『比企筋』最後の女性であったというのが『政子の悲劇』であったとかんがえますが、政子は既に『鞠子』が2歳の時から育てた自信があり、そのことは気にならなかったのだと思います。
1221年、承久の乱の『政子の大演説』は『鞠子(竹御所)』の将来を想定して、最後の雄叫び(全身からの)であったと考えると、痛々しい話である。
1219年、既に、鎌倉の地に下降していた三寅(藤原頼経)はその時点で4代将軍として考えられていたし、『鞠子』が『御台所』になることも『政子』の胸中では固まっていたと考えるのが妥当である。
総てが、『源氏の血』…『鞠子』一筋で進められていたと考えます。
それは、比企筋(頼家と若狭局)の鞠子では無く、2歳から手塩にかけた『政子の孫娘』としての『竹御所』として、すっかり『嵌まり込んでいた』のが実態であろうと想像いたします。
それほど、女性『政子』にとって、関東:武蔵の後家人達(武士団)が源家3代の後を狙っていた脅威は恐ろしいものであったと言うことです。
兄弟の二代執権『北条義時』だけが頼りであったのですが、1224年承久の乱から3年後急死している。
翌年1225年に北条政子も69歳で卒去するのであるが、末期の『政子』の人生は淋しいものであったろう。と推察します。
そんな中でも、唯一の光が『鞠子(竹御所)』と『三寅(藤原頼経)』の行く末を考えることであったと思う。と…
晩年は、『源頼朝(鎌倉将軍)』の行く末を夢見て、死んでいった『乳母』の『比企尼』に通じるものがあります。『北条政子』もすでに『菩薩』になっていたのであろうか?
すくなくとも、『鞠子(竹御所)』は皆のそのような『熱い気持ち』を一身に受けて、毎日を過ごしていたと考えると、比企筋の恵まれない悲劇の女性達のなかで、やっと咲いた『一輪のひまわり』であったのではと考えます。
1225年の政子の死から1234年の『竹御所』の死まで実質10年間が『比企一族』の『木漏れ日の時代』として、輝くのです。
続きは次回へ…
| [38] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年09月07日 21時03分02秒 ) | パスワード |
 |
では次回楽しみにしております。
| [39] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年10月04日 22時01分15秒 ) | パスワード |
 |
朝日新聞社から発刊されました…
宮尾登美子さん執筆の、宮尾本『平家物語』1巻(青龍之巻)を一気に読みました。
宮尾さんにかかると『平家物語』もこんなに『華やか』になるのだなあと感心させられました。
「テンポ」の速さもさることながら、良く勉強されているなあと感銘しました。
彼女が今を代表する『女性作家』であることは誰しも認めるところですが、特に女性の虐げられた中から、強く逞しく生きる『粘っこいしたたかさ』のようなものを書かせたら右に出る者はいないと何時も感心させられます。
今回は少し趣を異にした『華やかな』男世界を書き下ろしていらしゃるのですが、
日本文化(女性蔑視)を史実に基づき認めながらも、『物申す!!』を代表する大作家(平成の紫式部)だと思います。
話は本論に移りますが、
『白河院』のご落胤としての『平清盛』を紹介する下りがある。
平忠盛(清盛の養父)が鶴羽(白河院のお手付き)を貰い受けることを、友人藤原為忠の表現として…
『古女頂き(ふるめいただき)』と言って、貴い方より女性を頂くのは、よくある話で平安時代、鎌倉時代には『出世の常道』であった。と明言している。
『白河院』等は行き先の解らない子供(及び女性)がたくさんいたと言われている。
『ご落胤』の好きな小生としては是非、この『古女頂き(ふるめいただき)』と言う言葉を頂かねばと思いここに記します。(竹御所とは直接関係のない話ですが、)
私が『頼朝のご落胤』とする『島津忠久』『安達景盛』『北条朝時』にかかわった『丹後内侍』も『姫の前』もいずれも、源氏の棟梁『源頼朝』の『古女(ふるめ)』であったのではないかと考えたのです。
『古女頂き(ふるめいただき)』の多くは、お腹に妊娠した状態で配下の信用の於ける者に下げ渡すのが常であったそうです。
考え方としては、子供を養子として『養父母』に育てさせる考え方なのですが、願わくば『実母』連れで、守られながら、育つ事が望ましいとの、父親の思いからそうしたと考えられます。
貰い受けた『配下』の側は、その尊き女性を『床の間』に飾り「手を付ける事無し」に大切に扱うのが常で、人によっては『後』にも、元の主人が『お渡り』になることがあったとされる。
その場合は『次の子供』も『ご落胤』と言うことになる。
その考え方によれば、惟宗広信が『古女頂き』後の、島津忠久の弟『若狭忠季』と…
北条義時が『古女頂き』後の、北条朝時の弟『北条重時(極楽寺流)』が怪しいと見なければならない。『北条政子』の目を盗んで、子造りに励んでいたのではないか???
と想像すると…
『頼朝』も本当は『政子』のことが既に『嫌』になっていたのかもしれない。
話は変わりますが、10月30日(日曜)の大河ドラマに又々『私の恋人』である『桔梗』姫が登場しました。
今度こそ本当の最後になったのですが、
『恩赦』で佐渡遠島から解き放たれた『桔梗』が『足利家』に身を寄せる下りがあって、『桔梗』は前夫の足利泰氏のご落胤捜しに奔走することになります。
あくまで、ドラマの上での話でありますが、シナリオでは松浦党の『桐子(とうこ)』姫が『泰氏』の子であるという設定ですが、『高師氏(江原真二郎)』と一緒に博多まで探しににいって、『桐子』に一度断られて、「メド」の立たないままで、父親代わりのような『高師氏』に切られ抱かれながらの最期でした。
私の恋心が深く考え過ぎでのことだとおもいますが…
『桔梗』姫の迷える『霊』が再登場した理由は、『桔梗』を通じて…
① 晩年の北条政子が『竹御所』に救いを求め、総てに疑心暗鬼になって、北条義時と死別した後、特に思いが『竹御所(孫娘)』に執着していったことを『桔梗』の演技の中にみました。
② きっと、政子の晩年は『三寅』と『竹御所』に総ての夢を賭けたのだとおもいます。そして、現実には『竹御所』と『九条頼経』に裏切られるのです。
③ 実際には勝利したはずの『承久の乱』での京都朝廷との戦いが結果として敗戦であったこと、そして後家人筆頭の『三浦家』(比企の本家筋)が成り上がり『北条家』を足下にしたということです。
④ 『三浦家』も一度は『北条家』の上座に座ったのです。
『竹御所』とともにやってくる、しばらくの『比企家の木漏れ日のさす日々』は1225年の政子死去の日から1234年の『竹御所』死去まで、厳密には北条時頼のク-デタ-の日(宝治合戦…1247年)の『22年間』続くのである。
全ては、『京都朝廷』派閥とともに、鎌倉に下降してきた『親王将軍』と共にあった『名越流北条家』『三浦家』『足利家』の影で「比企家」が残っていたと言うことです。
もう一つの想像は、『とうこ』です。『桔梗』姫が見つけた『足利の姫』は『桐子(とうこ)』で1333年鎌倉(北条)の滅亡の足利尊氏の正室(赤橋流北条登子(とうこ))は『比企藤内朝宗の娘(姫の前)』の末裔である。
『桐子』=『登子』を彷彿させたということです。
今度こそ、『桔梗』さん、成仏してください。お願いですから! 以上
| [40] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年10月04日 22時24分57秒 ) | パスワード |
 |
「北条時宗」はすごく捻った内容なんですねぇ。
時輔さんが生きてたのにはビックリしましたが
桔梗さんはもう1度敗者復活戦をやるのですか。
それが「桐子」だったとは。
桐子にはなにか秘密があるのかな?とは思ってましたが。
「古女頂き」は江戸時代の表現では「拝領妻」でしょうか?
(劇画漫画の見過ぎ?)
江戸時代で「古女頂き」または「拝領妻」で有名なのは柳沢公ですね。
綱吉の女を下げ渡されたとかで
この女性の生んだ男の子が綱吉の唯一の嫡男だったとか噂がありましたね。
それにしても桔梗さんというか比企の女性の執念は裏が読める人にはたまらないですね。
| [42] |  | 林原英祐さんからのコメント(2001年10月29日 20時29分16秒 ) | パスワード |
 |
最近、流行っている京都の『晴明神社』(上京区堀川通)…『陰陽道(安倍晴明)』によれば、一種の物忌に類する方術で、居住の家から出向う方位が凶方であれば、それが吉方にあたる方位の家に一夜を過ごして行くこと。
平安中期以降、貴族社会に盛んに行われた風習である。
そのことを『方違え』といい、高貴なお方の証明にもなる。と………
吾妻鏡にこの『お方違え』が言葉として述べられているのが、物の本によれば、87回を数えることが出来る。と、……
勿論、京都の公家の作法であり、4代将軍『藤原頼経』以降の話であるが、回数の多い方を順にあげると、
①藤原頼経(4代将軍) 35回
②宗尊親王(6代将軍) 22回
③竹御所 (頼経の妻) 13回(内、頼経と同時1)
④藤原頼嗣(5代将軍) 10回(内、頼経と同時2)
⑤源実朝 (3代将軍) 5回
⑥北条政子(頼朝の妻) 2回
⑦宗尊親王の御息所 2回
⑧北条義時 1回
……と『竹御所』は女性としてはNO.1
『野口実』先生はこのことを引用されて、『金吾将軍姫君』、後の『竹御所姫君』そして、『竹御所』、、、4代将軍頼経の『御台所』が中世イエ社会の『政子』の『嫡女』としての存在感を表していると明言されていますが、……
そのことで、『竹御所』が鎌倉幕府のフォ-マルな地位にいた…証明になります。
その『竹御所』を中心にして、『反北条氏』の『群団』が形成され始めていたのです。むしろ、歴史的な背景としては1242年、3代執権『北条泰時』の死後に北条氏による『執権政治』の『危機』が具体的に起るのですが、
少し前に、4代将軍『頼経』を中心とした『三浦氏』『足利氏』『名越流北条氏』の群団が形成されており、鎌倉幕府(頼朝)開設来の『将軍』を中心とした幕府運営を再度模索していたきらいがある。
『北条』離れの動きであったと考えます。
『竹御所(頼経の妻)……源氏の血流(源頼家の娘)』が『御家人』達の最後の『拠り所』であったことは事実であり、その中心に『三浦家(北条泰時の…)』があったのも確かです。
その『三浦一族』を滅ぼすことが『北条氏』のテ-マになったのです。
1234年に起った『竹御所』の悲劇(男児死産、産後32歳死去)は、『頼経』中心の鎌倉幕府そのものの『夢』を打ち砕いたと言えます。
北条時頼による『宮騒動』(1246)や『宝治合戦』(1247)は一般に『北条氏のク-デタ-』といわれていますが、『北条得宗家』による専制政治体制への入口であり、正に、『北条一族の陰謀』といえる出来事であったと思います。
『竹御所』を通じて存在した『比企一族(比企系図)』はその意味では、『初代将軍頼朝』『二代将軍頼家』『4代将軍頼経』と常に『鎌倉将軍』を立てる立場で筋を通した存在であったと言うことです。
『三代将軍実朝(三浦家)』を考えると『一貫性』のある『比企尼』の教えに忠実な生き方を貫いていたと言えます。
その意味では『北条(下級武士)』の配下(彦)にはならなかったと言うことです。
『梶原氏』『畠山氏』『和田氏』『比企氏』『三浦氏』は最後まで『北条氏』と対決した形で存在したと言うことです。(『NO!』と言える御家人達である)
最後の『御家人』といわれる『安達氏』は『時頼』…『時宗』…『貞時』と『北条得宗家』に仕える『我慢の御家人』を努め全盛期を迎えるが、1285年に『北条家御内人』の平頼綱に煮え湯を飲まされる結果になる。
いわゆる『霜月騒動』である。
『比企家』のその後についてですが…
>江戸時代の初頭の話、徳川秀忠に仕える『比企家(600石)』が実在したと聞かされますが、名誉ある武士の血筋として『召し抱え…』の理由にされたと記録が残っています。
>同じように、『伊達家』に仕えた『比企家(300石)』も血筋によって『召し抱えられた』とあります。
>最後に越前福井松平藩に仕えた『比企家(400石)』(小生の母方の実家)は初代『比企数馬』が12歳に400石で召し抱えられたとあるが、理由が定かでない?
『竹御所』さんを初め、『姫の前』さん、『若狭局』さん、『丹後内侍』さん、『比企尼』さん等の『沢山の無念の最期』を思い出すとき、
人が安易に迎合する現代社会(平和)の中にあって、『自らの信じる所を生きること!』の難しさと尊さを教えられる気が致します。
そして、その先生方が『全て女性』であると言う所に、比企一族の誇りが存在すると考えます。
難しくなりましたが、『竹御所』の供養といたします。
私が今日あるのは、貴女方のお陰であります。大切に生きます。 <合掌>
| [43] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年10月30日 10時37分02秒 ) | パスワード |
 |
「方違え」の回数からも竹の御所がどんなに大切にされていたか
分かりますね。
変なのが付いたら困る、と無事に安全にと人々が奔走してたのが分かりますね。
また「血筋」ということで召し抱えがあったのですか。
「家」の存在意義について改めて考えてしまいます。
本当に貴重なお話をありがとうございました。
また思い出したりなさった事がございましたらお書きになって下さいね。
楽しみにしております。
| [45] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年11月05日 00時05分44秒 ) | パスワード |
 |
<29>の島津忠久関連ということで「彦熱」まいふぇばりっと<その4>と重複:
メールを頂きました:
行って来ましたよ、片瀬の常立寺。
ついでに源頼朝、大江広元のお墓も見てきました。
道はめちゃくちゃ混んでましたけどね!
最初に、逗子市を経由して行ったの。
それで、「披露山公園」というとこに先ず行った。
名前の由来はさっぱしだけど、逗子市小坪にある山で、
山頂から湘南を一望できました。
すっごい、きれいだったよ~。
それで当初の目的、元使塚がある常立寺に行って来た。
杜世忠ら3人の辞世が石碑になってました。
僕が見学のオッサン夫婦に辞世の詩を解説してた時に、団体の見学者が来ました。
地元の人でしょう。
常立寺は小さいお寺でしたので、境内が人でいっぱいになった。
ちなみに、お寺のおばあさん(おそらく住職夫人)によると、
正式には「じょうりゅうじ」と読むそうで、地元の人は訛って「じょうれんじ」というそうで
す。
その後、飯食って、
鎌倉経由で帰ったんですが、
時間があったので大江広元の墓を見ました。
思ったより山奥にあって、徳川時代に長州藩が造ったものだそうです
(毛利氏は大江広元の末裔だから)。
広元、毛利季光(広元息で毛利氏開祖)の墓のすぐ横にもう一つ墓があったんで
地元のオッサンに尋ねたところ、
島津氏の開祖・島津忠久のお墓だと。
因縁めいてるなあ、と思いました。
| [46] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年11月05日 01時31分35秒 ) | パスワード |
 |
メールを頂きました:島津忠久・頼朝のご落胤説に反対の方からです
「島津氏=頼朝落胤」説は徳川時代に造られた大うそです。
島津氏はもともと京都の貴族「これむね」氏出身だから。
島津氏が頼朝の子供でないことは、
頼朝の奥州征伐の時、島津忠久がもらった軍忠状からも明白です。
年齢的に考えて、島津忠久が頼朝の子供である可能性はほとんど有り得ず、
今まともな史学者はこの説を誰も信じてません。
島津さんご自身も信じてないでしょう。
だって、足利時代までは夢にも「頼朝公の末裔」とは自称できなかったろうし。
(やったとこで誰も信用しなかったろうし)。
島津氏が、いきなり薩摩・大隅・日向の三国守護に任命されたのは理由があって、
この三国にまたがる「島津ノ庄」の地頭に任じられたからです
(これが苗字の由来)。
この島津ノ庄は、今の青森県にあった外ガ浜庄と並んで、今で言う「一県まるごと」
包括されるような広大な庄園でした。
だから、この三国で一単位にしなきゃ、まともな行政なんてできなかったの。
梶原景時も山陽道で三国守護に任じられたからさ。
古代の国司と違う。
やっと完全に「日本領」にした奥羽を他地域のように細かく分割せず、
旧郡をそのままにしたのも、
行政単位の要求する合理性が変化していたからでしょうね。
それ言ったら、大友氏はなぜ豊後(頼朝の知行国)守護になり、武藤氏(少弐氏)は太宰府を任されたのか?
大友氏は波多野氏の庶流の小豪族だったし、武藤氏はもともと頼朝に敵対して降伏した藤原氏に過ぎないよ?
島津氏がもし優遇されたとしたら、それは比企氏の一族だったからでしょう。
島津忠久のお母さんが比企能員の妹だったから。
だから、島津氏は比企氏の没落とともに、大隅と日向を免職されてしまいまし
た。
島津ノ庄も薩摩地域のみの地頭にされちゃった。
ホントに頼朝の落胤だったら、絶対殺されてるって。
北条氏じゃなくたって、そんな危険な分子は殺すに決まってんじゃん?
頼朝兄弟の子孫で吉見氏が生きながらえたのは、取るに足らない小さな武家でしかなかったから。源範頼の末裔だもん。
| [47] |  | 服部 明子さんからのコメント(2001年11月07日 22時36分41秒 ) | パスワード |
 |
<46>への反論です。メールで頂きました。
『源頼朝、大江広元のお墓も見てきました。』
これは非常に素直な方ですね。
「案内書」の通り、という感じですから。
両方とも島津家が、建て直した物でしょ。
本当の頼朝の墓は、勝長壽院(跡)ですよ。
どうも、墓は掘り出せなかったみたいですね。
私は、宅地造成で粉々にされたか、今だ人知れず地中にあるかと思っています。
本当の大江広元の墓は、鎌倉アルプスと言われる、山の尾根。
明王院側から登って、「はじめ弁天」を通り過ぎて、しばらく行くと七重石塔が
何の案内も無しに立っています。
両方とも、静かな人が少ない場所。
「それじゃなんだから」と引っ張り出してきたんだろうか。
可哀想な二人。
しかし、本当の墓に行くことを奨めるよ。
鎌倉を書くなら、もっと勉強せい!
島津氏の宗家は忠久。
その子は、頼朝の子、なんて当り前の話。
何処で育ち、母親は誰だったか。
そこまで調べろって。
そこへ行けって。
| [48] |  | 林原英祐さんからのコメント(2002年01月08日 20時31分27秒 ) | パスワード |
 |
しばらく、ご無沙汰していましたがーーー
何か、当該スレッドの締めくくり(落ち!)が必要と考え、お正月でもありますから、お許し頂いて書き込みました。これで終わりにします。
又、夢を見ました。
『竹御所』の『謎の供養話(少し、いやらしい夢見話か??)』
野口実先生の竹御所小論…鎌倉幕府政治史上における再評価の『むすび』の項に…
…『最後に、ひとつ謎を提示したい。それは『吾妻鏡』嘉禎元年(1235)7月27日条に「竹御所姫君於相州御亭。有除服之儀」と言う記事を載せていることである。竹御所の喪に一年服した姫君とは誰なのか。
「吾妻鏡」編纂時の錯簡なのだろうか』とロマンを込めた書き方でむすんでいらしゃいます。
もし、実在する姫ならば、源氏最後の血流として、興味をそそる話である。
『いつもの通りすがりやさん』に頂戴したHPの文脈によれば、この姫は実在した姫で。1234年の『竹御所』男児の死産による死因になった。
『実姉』であったことになる。
しかし、通りすがりやさんも、この1235年7月27日以降のこの姫の消息が不明といわれ、多分若く死亡した為であろうとされていた。
小生が、暇に任せて、『吾妻鏡』の記事をクリックしていましたら、こんな記事にであった。
1235年(嘉禎元年)11月14日
京都の使者参着す。10月28日に将軍家の御姫君(御他腹、御年15)御卒去と。
11月15日、将軍家御除服。
南門に出御し玉い、御祓いの儀有り。
晴賢これを奉仕す。
この『将軍家御姫君』が『竹御所姫君』であると考えられます。
『御年15歳』を逆算すると1220年生まれと言うことになり、三寅(頼経)が1117年生まれとすると、3歳の時(承久の乱の年)の子供と言うと、当然『頼経』の子供ではない。
1220年は『竹御所』が18歳で、源実朝が1219年に28歳で殺されていることから考えると、実朝は『竹御所』懐妊を知っていたのであろうか?
その日から逆上ること3年(1216)に『竹御所』は14歳で実朝夫人の猶子になている。その時、25歳であった実朝の生前の出来事である。
私は、蒼白い顔をした『平家の面影』に似た『歌読み人』を想像してしまう『3代将軍源実朝』が最初にみそめた「初恋の女人」が『竹御所』であったのではないか、と考えてしまうのです。(私は頼家が存命中からの関係だと考えている)
北条政子の計らいで実朝夫人(坊門)の猶子になったのは、その故の婚儀であったと思うのですが、想像は余りにも、突飛で少し強引すぎるとも思いますか?。
● 1230年の出来事、藤原頼経(13歳)と竹御所(28歳)の結婚
● 1216年の出来事 竹御所(14歳)が実朝夫人(24歳)の猶子
当時、源実朝(25歳)の事である。
上記を対比して見て見ると、女性(竹御所)中心に考えると実朝の妾の方が何か現実的で絵になる話だと思いませんか??
かって、『姫の前』(比企藤内朝宗の女)が源頼朝の官女から、北条義時に下げ渡された話をもって、北条(名越流)朝時が源頼朝と『姫の前』の子で懐妊後に「北条義時」と偽装結婚をさせたのだと断じた『嫌らしい想像』と似ている。
この話も、その種の話に入る話ですが、 夢に出てきた話として書き残したい。
竹御所にとって…
4代将軍藤原頼経との婚儀は再婚話で、『竹御所』の子連れ結婚と言うことであうか?
1230年には、『竹御所姫君』は既に『11歳』に成っている。
又、記事にある将軍家御他腹とはその時点での後室『内大臣藤原家良女』(頼嗣の母)からみての表現として『竹御所』腹は『御他腹』と言うことになるのでしょうか?
1216年(竹御所14歳の時)に実朝夫人の猶子となる下りがあるが、その辺りに長女(姫)の父親の謎が秘められているのではないでしょうか?
実朝未亡人(坊門家OR実朝筋)の周辺に種(父親)が存在するのではと考えます。
『竹御所』が28歳で初婚であったとは当時としては不自然な考えであり、むしろその『姫(長女)』の方(父親)が『本命』の結婚相手であったと考える方が、年齢的にもずっと自然であると考えます。(本命とは実朝を指す)
私は、大胆な推測として、竹御所が源実朝の『妾』であったのではと考えている。実朝が『公暁』に1219年に暗殺されて、余りにも早く正室が京都の坊門家(里)に帰っているのが気になる。
1216年に実朝夫人の猶子となり、1219年に実朝が暗殺される3年間の間に『長女(姫)』が産まれているということである。
実朝暗殺時点(1219年)にて『実朝』28歳、『竹御所』17歳と言うことで、年齢的な不自然さは無い。
又、仮に、1220年生まれとしたら、実朝暗殺時点にすでに竹御所が懐妊しており、実朝暗殺後に産まれた『姫』と言うことではないか??
悲運の星の下に産まれた『竹御所御姫君』が『竹御所』の一周忌を喪に服し、その僅か3か月後、自らも後を追うように『15歳』の若さでこの世を去った。のでは?
蒼白く、知的で『平家』の匂いのする、3代将軍『源実朝』の実子が『姫』であり、実朝の実姪の『竹御所』が母親であった。この1235年10月卒去した『将軍家姫君(御他腹)』こそが『源氏最後』の血筋の人であったのではと考えている。源実朝が女人を近付けなかったという逸話があるが?『竹御所』故では?
僅かな、慰めは、『竹御所』の一周忌(喪)を実の娘が勤めたということが、坂東武者源氏の棟梁の血筋の最後の儀式として、『自己完結』になっている点・北条一族に対する『意地』のようなものを感じ『晴れ晴れしい』気持ちである。
『竹御所』そして『その姫君』(源氏最後の血)安らかにお眠り下さい。
少し供養も行き過ぎましたかね? この話を『比企一族』スレッドの落ちとします。 合掌
(完)
| [49] |  | 服部 明子さんからのコメント(2002年01月08日 22時36分53秒 ) | パスワード |
 |
謎が謎を呼びますね。
鎌倉にはあんまりロマンに満ちたお話はありませんが
竹御所の秘められた恋?!
夢だけでは済まないような秘密のロマンを感じます。
ありがとうございました。
| [50] |  | 林原英祐さんからのコメント(2002年09月03日 20時07分34秒 ) | パスワード |
 |
前編追章 資料(比企系図より)その後の比企筋
やっと、拾い読みが出来ましたので、参考までに末尾に載せておきます。
年代を解りやすくするために、西暦年号で書き込みました(挿入)
①比企藤四郎能員(鎌倉比企家) 仕源頼朝卿頼家卿 領武州比企入間高麗三郡都合35万石 建仁3年(1203)9月2日北條遠江守平時政被誅(比企尼養子)
②比企四郎時員 父同時自害(比企の乱)
③比企伯耆法印圓顕 父能員伏誅之時圓顕2歳母共に被配流安房国7歳之時従房州庵鎌倉 (鎌倉妙本寺)出家号圓顕後赴京都東寺為真言之学匠亦下鎌倉住山内證菩提院
④比企次郎員茂 實者時員男也時員父能員同日自害之時員茂胎内其母退鎌倉赴武州比企郡隠民間産於員茂後同国比企郡岩殿観音堂別當被養育建保6(1218)寅年月日員茂16歳亦上洛以伯父伯耆法印助成奉仕順徳院為北面承久3年(1221)巳年7月日順徳院佐渡国遷幸之時奉慕即跡越後国住寺泊於是称名寺泊右兵衛尉
⑤比企小太郎員長(竹御所領地) 其頃鎌倉将軍頼経卿御臺所者頼朝卿嫡孫亦頼家卿之息女竹御所母儀産於越州為若狭局者比企判官能員女也似之比企吉見二郡為竹御所之領地員長依為被御所親密似自越後国帰比企郡居住焉 弘長元年(1261)酉年2月2日卒
⑥比企左馬允満長 始亦筑城武州中山村居住焉
⑦比企右衛門佐守長
⑧比企小四郎之長
⑨比企内匠助重長 法名 宗善
⑩比企藤次補榮
中村藤三郎重伯 其子 中村与八郎重之(相州)
中村四郎兵衛重友
⑪比企藤兵衛尉久榮 明応8未年(1499)月日於武州廣木大佛城討死
女子 古川勘ヶ由妻 丹波常吉母
女子 古川勘ヶ由継母
女子 木呂子清兵ヱ妻
女子 西郷左京進妻
⑫比企右衛門尉晴榮
比企左馬允員信 其子左馬允能次
⑬比企左衛門尉秀長 上杉正榮ト有僚故退武州比企郡蟄居同州中山村
⑭比企藤四郎員長 左ヱ門佑
⑮比企藤四郎包永 左ヱ門 母古川丹波常吉女 同姓加賀守員政襲比企惣領職属上杉憲政国煎包永僅采 天文12年(1543)11月日没
⑯比企藤四郎榮興 佐左ヱ門 実者古川縫殷助常成次男 仕北条氏直居相州鎌倉比企谷是先祖能員居住之地也 文禄4年(1595)未年月日不知於相州没
⑰比企藤四郎義包 始古川主膳 改源氏 母相州住人中村又右ヱ門女 生相州 出江府 仕上総介忠輝君元和元年(1615)相州蟄居 同6年(1620)年月日不知没歳49
女子 比企佐五右ヱ門員重妻
女子 海野次太夫妻
女子 古川久七郎氏運妻(武州赤山住人)
⑱比企義英 古川主計(後比企氏)其子 藤藏
其 左左ヱ門
女子
女子
藤三郎
藤五郎
⑲初代比企数馬義重(藤四郎義包次男)1617~1689 越前比企家(別家?)
比企藤四郎(嫡男) 板取駅で自害 松平権蔵騒動の故か?
2代比企四郎兵衛榮翦(山原傳左ヱ門友勝次男)養子1666~1710
3代比企佐左衛門榮搶1684~1731
4代比企文左衛門榮禎1717~1785
5代比企佐左衛門榮脩1749~1816
6代比企佐左衛門榮庸1783~1847
7代比企五郎左ヱ門榮信1815~1850
8代比企幸次郎榮貞(本多門左ヱ門次男)養子1827~1852
9代比企他五郎榮徴1840~1889
○比企外五郎福造1845~1884(別家:御影比企家)其子『比企雅』1883~1959其子 林原禮 其子◆林原英祐
10代比企三五郎儀長
11代比企虎五郎忠 其子 比企元 其子 比企修 其子◆比企知子
以上です 2002/9/3
| [51] |  | 服部 明子さんからのコメント(2002年09月03日 22時28分27秒 ) | パスワード |
 |
西暦に直すのも大変な時間がかかります。
お疲れさまでございました。
比企一族のご子孫の方には大変に参考になりますね。
どなたかからご連絡がありますように。
| [52] |  | 林原英祐さんからのコメント(2003年10月13日 11時01分02秒 ) | パスワード |
 |
突然、見知らぬ「伊藤」さんと言う方からメールを頂戴しました。
原文のまま、ご紹介します。
『林原様』以下引用文
「私の母の旧姓は比企といいまして、母方の祖母(母の母)から比企尼に関わる
比企家の家系であると聞いたことがあります。今春、母を伴い鎌倉の妙本寺に
いって参りました。母もこのことがきになっていまして旅行ついでにいったのですが
、そこでわかったことが母の実家と宗教が違うようなのです。比企家を関わる家系
でこのようなことはあるのでしょうか。ご存知でしたらご教授できれば幸いです。
因みに母の実家は古くからの豪農であり、母も人の土地を踏まずに学校に通って
いたほどですので全くのデタラメではなさそうなのですが。住所は新潟県北蒲原郡
紫雲寺町長者館です。」
小生からの『返信』文です、、、
「メール拝見しました。
小生も素人の興味半分で始めました勉強ですから、、、
そんなに大したことは申せないのですが、、
仏教(宗派)や神道など、現在の考え方と昔(特に戦国未明)とでは全く考え方(単独の宗派などなかった)が異がうようです。
そのことを一番端的に教えられたのは、ご承知の「真言宗」の本山である「高野山」を訪れた経験のある方が感じられる、、「奥の院」にむけての「墓標」であります。日本の有名な歴史上の人物はもとより、江戸時代の有名な「大名」や「旗本」は全て「真言宗」かと誤解してしまいます。
ちなみに、「比企」のことを勉強しまして、、、、
「妙本寺」の開祖とされる比企能本(円顕とも)は京都の東寺(真言宗)の学徒として出家修行した。その後「日蓮宗」に帰依して「妙本寺」云々とあります。
福井越前松平藩に仕えた「比企」はその菩提寺から「浄土宗ー京都知恩院」ですが、系図の中に出てくる。比企家だけでも戒名などから判断して、、
「真言宗」「禅宗(曹洞宗ー永平寺)」「禅宗(臨済宗ー比叡山)」「浄土真宗」「日蓮宗」など雑多な宗派が散見されます。
だから、疑問の件は大した意味がないことだと考えます。
又、比企家の本当の紋所は「丸菱」(甲斐武田家の紋)だとされていますが、これも福井越前比企家の紋は添付いたしましたような紋所が伝わっています。日本に長く伝わった「女紋」の話、などを考えますと「紋所」も余りはっきりとは言えない部分があると思います。
今回のお便りで、うれしかったのは、、、
①新潟(北陸)にきっと「比企家」の方がいると信じていました(天の声)のが、実際にいらしたということが感激です。私の私見では越前福井よりは新潟の方が「比企家」の郷としては相応しい地域だと考えています。
比企家は「武蔵国」が本来の土地なのですが、、「本家」筋は武蔵から、、上杉家、伊達家、徳川家、松平家などに分かれて仕えていったと考えられています。
②次に、あなたが短いメールの中に書かれてあります、、、
自分は「伊藤」と申します、、母方の又母(祖母)が比企にゆかりのある者であると聞きます。云々、、、、
は、小生がこの「比企一族物語」の勉強を志した「動機」であります。「比企」が「女系一族」であるという仮説に当てはまることに、驚きを感じています。
この歳(61歳)まで生きてきまして、母は88歳で健在ですが、大きな声ではいえませんが、「余り良くない遺伝子」を持っているなど自慢の出来ることはありませんが、、、
この歳になって、時々「天の声」を聞くことがあります。これも遺伝子の中に組み込まれているのでしょうか、それだけは自信と誇りにしています。
平家物語の HPの先生(服部明子女史)によれば、日本(島国)にいれば8代で皆が親戚になるそうですから、、
多分、昔一緒に戦場で戦った(敵か?味方か?)仲間かひょっとしたら恋人(夫婦?)であったか?親子であったのかも知れないと考えますと、何か暖かいものが感じられませんか、、、
歴史学はそんな「主観的」なものであってほしいと常々念じています。
又お便りをください。歳と共に、暇になっていきますから、、、
丁寧なご返事がありました。
「林原英祐様 以下引用文
早速のご回答を有難うございます。
早速、母にメールをさせていただきました。
母も非常に興味津々なようで実家(比企家)に連絡をとり、
頂いたメールで家族会議を開くようです。
また、ひとつ親孝行できた気がします。有難うございます。
私もこれを機に「比企家」について勉強しようと思います。
是非とも、またご教授のほど、宜しくお願いします。伊藤
、、、以上が伊藤さんとの「やりとり」です。
| [53] |  | 暇潰しのギャンブラーさんからのコメント(2003年10月13日 11時37分56秒 ) | パスワード |
 |
林原さま
良うございました。女系比企家の面目躍如でございますね。名字は違っても血で繋がってるのですから。
宗教は途中の御先祖さまが勝手に自分の信条で変えてしまいますから
特に新潟でしたら日蓮宗のお家が多いでしょうね。
わたくしの新潟の親戚も日蓮宗ですしNYの親戚は禅宗ですし。
我が家は浄土真宗ですから子供心に我が家とは違うの?日蓮宗?禅宗?と不思議でした。馬鹿ですね~
紋も事情でいくらでも途中で替えますから。
我が家も江戸時代とうとう紋は本来の紋に戻す許可が下りませんでしたから
紋もこだわる事は無いですよね。
それより「比企家の本来の紋はXXで我が家は○○紋」と併用すれば良いだけのこと。
現在は紋の使用は自由ですから堂々とお使いになって欲しいです。
比企家の方々がいろいろな事情で各地に下ってそれぞれの地で栄え現在に至るという
事実は比企尼にとってなによりの供養でございますから
本当に喜ばしいですよね。
比企尼の血を受け継ぐというアイデンティティはこれからも御子孫の方に伝えていって欲しいと願っております。
| [54] |  | 暇潰しのギャンブラーさんからのコメント(2003年10月13日 11時41分58秒 ) | パスワード |
 |
新潟で伊藤さんとおっしゃいますと
我が家の親戚にも繋がるのかしら?
と・・・
日本人は8代遡るとみんな親戚と聞いていますがこちらでも繋がってしまうのかも。
本当に縁とは異なもの。
何重にも繋がるのでございますねえ。
しみじみ・・・
| [55] |  | いちはた としのぶさんからのコメント(2003年11月10日 23時38分53秒 ) | パスワード |
 |
私は若狭局と二代目との長子「一幡」の家系です。お初に御目にかかります。今年9月2日は比企一族全滅800年大遠忌日でした。鎌倉妙本寺の一幡と比企の墓には比企三郎様が蝋燭と線香の祭壇、ありがとうございました。去年7月と12月に父と母とを亡くした、その父母が京都六条西洞院の源氏のかっての邸宅群や若宮八幡宮のある、実家は五条で近いですが、この幼ななじみの場所に、源氏三代の記念の館を建造せよとの遺言でしょうか、ビル一棟を相続してくれました。鎌倉三代怨霊慰撫の慰霊塔にしたいとの思いです.どなたか、御知恵を御願いします。
千葉市稲毛区萩台町696の132 一幡叔伸
toshi-ichi@cnc.jp いつでもノックしてください。
よろしく。
| [56] |  | 暇潰しのギャンブラーさんからのコメント(2003年11月13日 00時27分27秒 ) | パスワード |
 |
一幡叔伸さま
京都でしたら京都府庁教育委員会または歴史編纂局のような所にお問い合わせなさってはいかがでございましょう?
どういう所でお知恵を貸してくれるんでしょうね?
| [57] |  | 井上さん からのコメント(2004年12月29日 04時46分23秒 ) からのコメント(2004年12月29日 04時46分23秒 ) |
パスワード |
僕の先祖は比企一族と因縁の深い河越重頼らしいのですが、出身が宮崎県南部の高城(薩摩藩北部)の旧家なんで地理的に怪しいですよね?
まあ 考えられるのは
1.島津忠久の西下に従った四男が先祖ではないか。
2.1185年に義経の義父にあたり縁座で処刑(斬殺)と伝えられる河越重頼ご本人が頼朝の誅殺から免れるべく西下した。
なんですけど・・・
| [58] |  | 暇潰しのギャンブラーさん からのコメント(2004年12月29日 06時29分56秒 ) からのコメント(2004年12月29日 06時29分56秒 ) |
パスワード |
>地理的に怪しいですよね?
全然怪しくないですよ~
3.南朝方として宮崎県南部まで転戦して下って行った、というのも考えられます。
4.江戸時代に名のある家は見つけ出されて士官の口がありましたからそういうのも考えられます。
その他にもいくらでも可能性はあります。
人間は移動するんですから。
ひょっとすると河越の一族の人が頼朝から地頭として派遣されたかも。
1番良いのは本家になるお家を見つけることだと思います。
で、系図や家書を見せて頂くことと思います。
「地理的に怪しいですよね?」なんて遠慮なさらないでください。
徳川将軍家の御子孫もアメリカ在住で日本語は全くお出来にならないという例もありますから。
西洋人なのに葵の御紋が好きで家紋にしちゃっている図々しいのもいます。こういうのは本当に「怪しい」です。
ふふふ
| [59] |  | 井上さん からのコメント(2004年12月29日 16時08分21秒 ) からのコメント(2004年12月29日 16時08分21秒 ) |
パスワード |
ギャンブラーさん
コメントありがとうございました。
あれからネットで調べてみました。そして本日、父が冬期休暇で帰宅し
写真や神社などの資料を見せてもらいました・・・それによると、
本家と称する「河越井上氏(高望系平家=比企氏と同祖)」はいろいろみたいです。関係者も政財界の大物(大臣クラスの国会議員や財閥代表など)を輩出しているみたいです。私の家も本家を主張してます。(笑)
→理由:氏神を祭る神社(高城町四家)への寄進も父が現在も大方しているようですし・・・家系図は見たことがないのですが、以下のサイトでは私の親戚が保有していたものが50年ほど前に焼失したけど、地元高校の研究家がそれ以前に模写したものが残っているそうです。
http://www.town-takajo.jp/syoukai/tyosi/006/016.htm
上記の著者は「平家」といえば源氏に滅ぼされた平清盛流れしか想定しておらず、源頼朝を守護した関東平家をすっかりお忘れのようで解説が支離滅裂です。(苦笑)
関東平家は鎌倉幕府創立初期の権力闘争でいろいろあったようですので「移動」というのはアリですね。
父に聞いたところ、「島津忠久の近習だろう」とのこと。
| [60] |  | 暇潰しのギャンブラーさん からのコメント(2004年12月30日 02時54分41秒 ) からのコメント(2004年12月30日 02時54分41秒 ) |
パスワード |
>私の家も本家を主張してます。(笑)
それで良いのですよ。堂々宣言なさってください。
昔は力のあった人は子供がたくさんいました。
天皇でも将軍でも子供の数が50人なんてありましたが
今では一夫一妻ですから忘れてますが
昔は高校生あたりの年齢で子供がいて少しもおかしくなかったんです。
正妻の腹の嫡子である男子は記録に残り易かったでしょうけど
また家の中での内訌で勝った方が今に続いているのでしょうけど
記録に残ってない家だってちゃんと続いてるんですよ。
ですから堂々「本家」を名乗って良いのです。
御所や天皇家や宮内庁に宣言して認められたものが勝ちですから
名を成してください。
昔の1970年代初めまでの戸籍謄本は身分が書かれてますから捨てないようにね。
ここ平熱でも立派な家の方達が来ていらっしゃいますよ。
>氏神を祭る神社(高城町四家)への寄進も父が現在も大方しているようです
神道は第二次世界大戦の敗戦で御加護が消えたとされて(日本人はゲンキンだから)今は世間から忘れられてますが
今でも凄い世界なんです。
神宮は別格ですが、神社でも賀茂神社や厳島神社など、なぜ続いているのか
それを考えたら凄い世界です。
寄進をするというのはなかなか出来ないことです。
お家が衰退してしまえば寄進も出来ません。
寄進出来るということはまだまだこれからも栄えるということです。神社と氏子は相互関係と思います。
ますます栄えるように御先祖さまを大切になさって神事に参加出来ると良いですね。
皆さんが生きてらっしゃる間に、
神社との関係が濃密である間に
家系図や家書の整理を早めになさってくださいね。
>関東平家
これは「坂東平氏」という名称の方が良いと思います。
平家=「伊勢平氏」ですから。
>鎌倉幕府創立初期の権力闘争でいろいろあったようですので「移動」というのはアリですね。
はい。
その土地その土地で教育委員会が歴史の編纂をしてるので資料を送って頂いたら調べられますよ。
県立図書館などにも置いてるそうです。
戸籍謄本をずっと遡って調べたら明治時代の初めにどこに住んでいたか分かります。
面白いですよ。
一生懸命読んでいたら御先祖さまから呼び掛けて来ますよ。
お彼岸やお盆に一族の長老からお話が聞けると良いですね。
お正月が来ますから最初の機会です。
どなたが系図を持っていらっしゃるか話題を出したら良いですよ。
| [61] |  | 鈴木房江さん からのコメント(2005年05月06日 03時14分50秒 ) からのコメント(2005年05月06日 03時14分50秒 ) |
パスワード |
お尋ねします。比企尼が「東松山市に住んでいた」と書いてありますが、もう少し具体的な史料はあるのでしょうか。比企禅尼は「鎌倉の比企ケ谷」に住んでいたのでは?。東松山市に隣接する鳩山町で、発掘された所謂、国分寺瓦にすでに「比企」とかいてありまっした。この瓦は8世紀のものです。
東松山市内にも「比丘尼横穴墓群」という遺跡がありますが、「比企禅尼」とは関わりはないと思います。「文字の印象がそうさせた」と思っています。もし、何か史料をお持ちでしたら、教えてください。
| [62] |  | のりかさん からのコメント(2005年06月05日 12時45分15秒 ) からのコメント(2005年06月05日 12時45分15秒 ) |
パスワード |
姫前さんは、頼朝の子供を身ごもって、政子に殺されるので義時にとつがさていますよね。そして産んだ子が名越一族になります。だって、名越の北条に対する反抗は凄いですよね。時氏とその弟も殺して時宗さんもやられてます。
政子は、頼朝も呪にかけて殺しその血が残ることを嫌がってすべて、自分の子供や孫さえも呪にかけてます。竹御前さんは、比企一族滅びた時政子に我が子のように育てられます。自分の分身として自分が死んだ後も操ろうとしました。でも、比企の血が強く倫理のわかる方でしたので、政子のマインドコントロールにのらなかったので、政子亡き後政子に呪かけられて死んでます。政子はありとあらゆる手段を使って、御家人の一族ほろぼしてます。まず、伊豆山神社の修験者、高野山の僧に密教で呪かけています。それは必ず体を硬直させる呪です。この呪をとかなければ比企一族も大変でしょう。
| [65] |  | 林原英祐さん からのコメント(2006年11月15日 06時46分46秒 ) からのコメント(2006年11月15日 06時46分46秒 ) |
パスワード |
お久しぶりです。ご無沙汰致しております。
7月で、リタイアー致しまして「晴耕雨読」人生の準備をしておりました。
「秋雨」の降る日、近くの本屋さんに行きましたら、書棚の奥から久しぶりに呼ぶ声が聞こえまして、、、、
「源平争乱と鎌倉武士」世界文化社2006.3.1、、これはビジュアル版「日本の歴史をみる」(全10巻)の第3巻です。
その中のP164、永井路子さんの「頼家と実朝」の稿の中で、、
>「吾妻鏡」は例によって、さりげない筆で、たった一行ばかりで書き流している。
>たとえば、頼家については、
>「男子が生まれ、比企尼の娘である河越太郎重頼の娘がめされ、御乳をさしあげた。」
>実朝のところでは、
>「巳の刻、男子が生まれた。阿野上総の妻の阿波局が御乳付に参上した。」
(中略)
>さて、それでは、実朝の乳母、「阿波局」とは何者か?
今日の話はここから始まります。
「比企一族」一辺倒の小生としましては、以前でしたら、「頼家」-「比企尼の娘」---と展開されるのですが、
「第二の人生」が始まりましたから、後段の、「阿野上総の妻の阿波局」が私を呼ぶのです。
昭和53年のNHKの大河ドラマ「草燃ゆる」の中で、「お姉さん!お姉さん!」と岩下志麻の北条政子を追いかけ続ける。真野響子の演じる「北条保子(これは多分、永井さんの命名だと思いますが?)」の印象的な好演を覚えていませんか、、、、私は何時も「へそが曲がっているのか?」側役の好演者のフアンです。この人が「阿波局」です。
少し前置きが長くなりましたが、、
私はもう一人の「阿波局」について興味があるのです。
宿敵「北条一族」の三代目執権「北条泰時」の紹介の中に、、これも一行コメントで「母、阿波局」と記されてあるのを拝見されたことがあると思います。
学者先生(名前が浮かばないのですが?)は、どこかで「阿波局」は北条義時の妹(時政の娘)でそんな名の「人」がいましたが、別人だと思います。と述べていらしたのを記憶しています。
まさか、北条泰時から伯母(父:義時の妹)にあたる人が「母」だとは考えられません。(義時と阿波局は兄妹にあたるから、、、)
私は、ひそかに「阿波局」同一人物説を推理(下品な、、)をしています。
話の始まりは「北条泰時」(得宗)と「北条朝時」(名越流)の位置取りが「いまだに、私の頭の中でしっくりこないのです!」
「朝時」の母は比企藤内の娘『姫の前』とされていますから、、『泰時』とは異母兄弟であるわけです。
さてさて、本日の『ダビンチコード』はこの辺にして、、次回をお楽しみにしてください。
| [66] |  | 暇潰しのギャンブラーさん からのコメント(2006年11月15日 07時41分36秒 ) からのコメント(2006年11月15日 07時41分36秒 ) |
パスワード |
林原さま
お久し振りでございます(ぺこり)
3年半前に引越しましたし名前も変えましたし(ふふふ)
「阿波の局」のお話を楽しみにしております。
スレッドが長くなっていますから
新しくスレッドを立ち上げてはいかがでしょう?
| [67] |  | 比企 員孝さん からのコメント(2017年02月01日 21時52分45秒 ) からのコメント(2017年02月01日 21時52分45秒 ) |
パスワード |
暇に任せて検索していましたら、この解説文にたどり着きました。とても詳しく調べられており驚きました。
私は政員の子、員重の三男、員定の末裔で十四代目になります。伊達家の江戸下屋敷勤めから伊予宇和島に来ました。次男も宇和島、長男は江戸でしたが、その子も宇和島に呼んだと系図に書かれています。いろんな方の調査結果で自分のルーツがより詳しく分かりありがたいです。 比企員孝
| [68] |  | 林原英祐さん からのコメント(2017年03月05日 22時19分39秒 ) からのコメント(2017年03月05日 22時19分39秒 ) |
パスワード |
最近は少しお休みしていましたが、いろいろ整理をしていまして、貴殿の書き込みを拝見しました。返事が遅れてすみません!お許し下さい。
ところで、比企筋は関東一円(産国:武州)と貴殿の宇和島藩(伊達遠江守宗利)直参200石~300石で西暦1600年代(江戸)栄えた記録があります。
小生が勉強した福井の松平藩の比企筋は同じ頃、江戸から維新にかけて、悪戦苦闘したおはなしです。
もし、ご興味がありましたら、メールを頂いたら(住所)資料を送ってもいいですよ、何かゴミ箱替わりにしているようで、、お許しを!
とりあえず、返信とさせて頂きます。
| [69] |  | 比企員孝さん からのコメント(2018年06月06日 13時42分21秒 ) からのコメント(2018年06月06日 13時42分21秒 ) |
パスワード |
友人の鎌倉観光に触発され久々に検索してみたら返信があり、びっくりしました。政員の子、員重は断家譜に掲載されていますが、我が家の系図によれば員重の次男『能成』三男『員定』(私は員定の末裔)は宇和島伊達の藩士に、後に長男『能成』の嫡男『員行』を宇和島に呼び宗利公に150石賜ったと記されています。今日は員長が竹御所から比企・吉見を譲り受けたとの記載が読めて中山に帰れた理由が分かり嬉しく思いました。
| 【 平家物語を熱く語る!!一覧に戻る 】 |
|
||||||||||||||
| ◇Copyright(C) 2000 c-radio.net. All Rights Reserved.◇ DB-BBS-system V1.08 by Rapha. WEB design Rapha. |